5.文献は語る -中国国史・その2-
(3).『三國志』魏書第三十烏丸鮮卑東夷傳
--------------------------------------------------------------------------------
三國志は、魏・呉・蜀の三国が鼎立していた時代(220~280)の歴史を、西晉の陳壽(ちんじゅ:蜀の人)が撰したも
のである。それ以前に、王沈(おうちん)の「魏書」、葦昭(いしょう)の「呉書」、魚拳(ぎょかん)の「魏略」が
存在していたが、陳壽が主に蜀書を中心に編んだものと思われる。魏志は「魏略」から多くを引用している。
陳壽は297年に65歳で死んでいるので、魏から晋の時代を生きていることになる。239年に、卑弥呼の使者たち
が洛陽を訪れたとき、陳壽はまだ子供だったが、卑弥呼の死後女王になった壱与が、使者を送った248年頃には既に
青年に達していた。つまり「三国志」は、3世紀を生きた人間がほぼ同時代の事をまとめた本なのである。中国の国史
のなかで、「三国志」が史書として極めて高い評価を得ているのはまさにその点にある。どこまで正確かはさておき、
より正確を期そう、より真実に近い描写をと心がけている姿勢が見受けられる。
陳壽の死後、多くの新しい資料が発見されたので、宋の裴松之(はいしょうし)が補註を加えて、陳壽の三国志の数倍
の分量にして429年に完成した。【魏略曰】の部分は裴松之が加えた補註。
-------------------------------------------------------------------------------
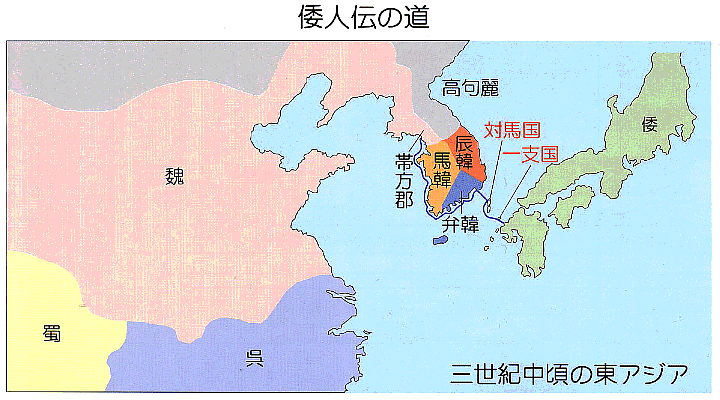
倭人在帶方東南大海之中、依山島爲國邑。舊百餘國、漢時有朝見者、今使譯所通三十國。從郡至倭、循海岸水行、歴韓
國、乍南乍東、到其北岸狗邪韓國、七千餘里。
倭人は帯方の東南、大海の中に在り。山海に依りて國邑をなす。旧百余国。漢の時、朝見する者あり。今、使訳の通ず
る所三十国。郡より倭に至るには、海岸に循して水行し、韓国を歴て、乍は南しあるいは東し、その北岸、狗邪韓国に
至る。七千余里。
倭人は帯方郡(今のソウル付近)の東南にあたる大海の中にあり、山島が集まって国やムラを構成している。もともと、
百余国に分かれていた。漢時代に朝見する者があり、現在、(魏の)使者が通じている所は三十国である。帯方郡より
倭に至るには、海岸に沿って水行し、韓国(馬韓?)を経て、時には南行し、時には東行し、その北岸(?)狗邪韓国
(くやかんこく)に到る。七千里余りである。
■漢書では「韓」の東南海中、後漢書では「楽浪郡」の東南海中となっている倭の位置が、ここでは「帯方郡」の東南
海中となっている。公孫氏が楽浪郡から帯方郡を独立させ、郡治も今のソウル付近に置いた。そのため魏朝の「韓」経
営の主軸は帯方郡に移ったものと思われ、以後の国史でも倭の位置を示す場合には同様の表記になる。これは、倭の魏
朝との窓口も、もっぱら帯方郡が受け持っていた事を示している。
■ここで興味を引くのは、「乍南乍東」という部分である。私は、「乍(あるい)は南しあるいは東し」と訳したが、
この部分を巡っては諸説が多い。「船の時は南へ下り、陸上へ上がった場合は東へ行く」とか、「南東へ南東へ」と訳
す人もいる。「南下しあるいは東行し、その北岸が「狗邪韓国」に至る。」という表現もおかしい。倭の北岸と見る説
が一般的なようだ。つまり魏の認識では、狗邪韓国は倭の一部だった事になる。
■帯方郡の位置を巡って近年、従来考えられていたソウル周辺ではないのではないかという議論が巻き起こっている。
帯方郡治の位置は、ソウル(京城)から開城付近というのが通説だったが、「朝鮮民主主義人民共和国」黄海道鳳山郡
文井面(沙里院)の古墳の内部で、積まれたレンガに「帯方太守張撫夷」の文字が発見され、帯方郡治は沙里院付近との
説も有力となった。倭はこの帯方郡を通じてもっぱら大陸の文化を移入したと考えられているのだが、沙里院が帯方郡
治だとすれば、その位置は楽浪郡とあまり変わらず、「楽浪郡を割いて新しく帯方郡を作った」という後漢書の記事と
は相容れないとする見方もある。
--------------------------------------------------------------------------------
始度一海、千餘里至對馬國。其大官曰卑狗、副曰卑奴母離。所居絶島、方可四百餘里。土地山險、多深林、道路如禽鹿
徑。有千餘戸、無良田、食海物自活、乘船南北市糴。又南渡一海千餘里、名曰瀚海、至一大國、官亦曰卑狗、副曰卑奴
母離。方可三百里、多竹木叢林、有三千許家。差有田地、耕田猶不足食、亦南北市糴。
始めて一海を度る。千余里。対馬国に至る。大官を卑狗といい、卑奴母離という。居る所絶島にして、方四百余里ばか
り。土地は山剣しく、深林多く、道路は禽鹿の径の如し。千余戸あり。良田なく、海物を食して自活し、船に乗りて南
北に市糴す。又南一海をわたる千余里。名づけて瀚海という。一大国に至る。官また卑狗といい、副を卑奴母離という。
方、三百里かり。竹木、叢林多く、三千ばかりの家あり。やや田地あり。田を耕せどなお食足らず。南北に市糴す。
始めて大海をわたること千余里で対馬に至る。其の長官を卑狗(ひく/ひこ)といい、副官を卑奴毋離(ひなもり)と
いう。この地の人々が住んで居る所は孤島であり、周囲四百余里しかない。土地は山ばかりで険しく、深林も多く、道
路は獣道のようである。千戸あまりの人口。良い田がなく、海産物を食べて生活し、船で南北(韓国や北九州?)にの
りだし交易を行っている。また大海を渡ると千余里で、壱岐に到達する。この海を瀚海(かんかい:現在の玄界灘)と
いう。長官を(対馬と)同じく卑狗といい、副官を卑奴毋離という。周囲は三百里ほど。竹木や草むらが多く、三千戸
程の家がある。少し田畑があるが、これだけでは生活できず、(対馬と)同様に韓国・北九州と交易している。
■壱岐・対馬の状況が、まさしく書かれたとおりであるのは実際に行ってみてわかる。学者先生達の本を読むと、ほぼ
同様の感想がつづられている。曰く「魏の使者はよく対馬を観察している。」「対馬は、まさしく倭人伝に書かれた通
りの、険しく森林だらけの島であった。」「来てみて良かった。実際に来てみると倭人伝の内容を体感できる。」など
など。名誉教授や博士などと言っても、感じるところは我々と同じである。
■対馬では、北九州の祭祀用具として用いられている「広型銅矛」の出土が異常に多い点が注目される。この青銅器は
北九州で製造されたのではないかと推測される。また北九州の弥生土器が大量に発見される事実も、すでにこの島が韓
ではなく倭に属していた事を裏付けている。
■壱岐の島では、「原の辻遺跡」が発見されて、ここが「一支国」の首都であったと言うことになっている。今までも
カラカミ遺跡など、弥生時代の遺跡は幾つか発掘されていたが、確かに現段階ではここほどの規模をもった遺跡は壱岐
の島にはないようである。壱岐・対馬ともに、長官・副官がいるので、彼らが駐留する首都が対馬にもあったはずであ
るが、対馬では今の所それに該当するような、弥生時代の大規模遺跡は発見されていない。峰町で最近、「山辺(やん
べ)遺跡」というのが発掘され、ここは大規模弥生遺跡という評判だが、まだ発掘整理中で報告書は刊行されていない。
(2004.1.1現在)
■【魏略曰】
「從帯方至倭、循海岸水行、歴韓國到拘耶韓國七千餘里、始度一海、千餘里至對馬國。其大官曰卑拘、副曰卑奴。無良
田、南北市糴。南渡海至一支國、置官至同對馬。地方三百里。」
--------------------------------------------------------------------------------
又渡一海、千餘里至末盧國、有四千餘戸、濱山海居、草木茂盛、行不見前人。好捕魚鰒、水無深淺、皆沈沒取之。東南
陸行五百里、到伊都國、官曰爾支、副曰泄謨觚、柄渠觚。有千餘戸、世有王、皆統屬女王國。郡使往來常所駐。/font>
また一海を渡る千余里、末盧国に至る。四千余戸あり。山海に濱いて居る。草木茂盛して行く前に人を見ず。好んで魚
鰒を捕うる。水、深浅となく、みな沈没してこれを捕る。東南に陸行すること五百里、伊都国に到る。官は爾支といい、
副は泄謨觚、柄榘觚という。千余戸あり。世々王あるもみな女王国に統属す。郡の使いの往来して常に駐る所なり。
さらに大海を渡る事千里余りで末盧国(今の佐賀県唐津市・東松浦郡)に到達する。四千余戸あり、 山際や海岸に沿
って家が建っている。草木が生い茂っていて、歩くとき前の人が見えない位である。好んで魚貝類を捕え、海の浅い所
深い所関係無しに、潜水してこれらを捕らえる。東南へ陸を行く事五百里で伊都国(今の福岡県糸島郡)に到る。長官
を爾支といい、副官を泄謨觚・柄渠觚という。千戸余りの人々が住んでおり代々王がいるが、皆女王国に統属している。
帯方郡の使者が常駐している所である。
■いよいよ日本列島本土に上陸である。一支国より末盧国へ至る行程も又、「千余里」と記載されている。魏の使節が
日本のどこに上陸したのか、倭人伝からはわからない。呼子、唐津、佐世保等々の説がある。わが馬野氏(歴史倶楽部
会員)のように、奴国や不弥国へそのまま直接向かったのではないかというような意見もある。説が混乱しているのは
一大国から末廬国までを「千余里」と倭人伝が記載しているからでもある。そもそも倭人伝の「一里」という単位には
一貫性がない。一里が何mに当たるのかは、局面局面で異なる。魏の使者が仮に壱岐勝本港から船出したとすれば、唐
津迄の距離は約50キロであり、石田港から唐津までの距離は約40キロとなり、壱岐島の最南端から東松浦半島北端
の呼子を結んだら約30キロとなる。これらを一里当りに換算すると50m以下ということになる。ここまでの行程で
は、一里はほぼ100m前後として考えられるので、むしろ「一海渡五百余里」とした方が正確であろう。となると、
倭人伝の作者はどんぶりで「千余里」と記録した事になる。或いは、「千余里」が正しかったとするとどうなるのか。
一大国より末盧国へ至る航路が、通説とは違うという事になる。つまり、末廬国は松浦半島周辺ではないことになる。
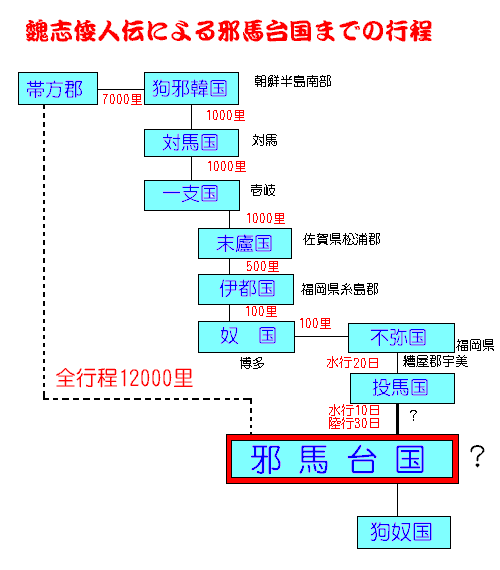 ■壱岐から千余里で到達する範囲は、西は長崎県の五島列島から、東は福岡県の宗像郡あたりまでの任意の地点が比定
可能であるが、しかしそうなると後に続く伊都国の比定地との整合性がとれなくなってくる。末盧国をどこに比定する
は、従来の通説は、現在の佐賀県東松浦郡.西松浦郡.北松浦郡一帯であり、松浦半島の北端の呼子港と唐津説に分か
れている。勿論この場合、見てきたように里数が合わないので、外にも神湊説(宗像)、福岡説、佐世保港説、西彼杵
(にしそのぎ)半島説、伊万里港説、前原市の「三雲、井原、平原付近」説等々がある。しかしながら、末盧国=松浦
半島唐津市説が距離的にも直線最短コ-スであるし、「マツラ、マツロ」と「マツウラ」との音訳比定を考えれば、こ
の地が末廬国である確立は高いと思われる。里程が合わないという欠点はあるが、やはり末廬国は松浦半島周辺(特に
唐津市附近)なのであろうと思われる。
■マツラはマヅラに通音し、はじめ末羅であったが、のちに松浦の字をあててマツラと呼ぶようになった。日本書紀巻
第九、神功皇后摂政前紀仲哀天皇九年三月ー四月の条に「因りて竿を挙げて、乃ち細鱗魚を獲つ。時に皇后の曰はく、
梅豆邏(めづら)國と曰ふ。今、松浦と謂ふは訛れるなり」とある。しかしこの記事は、日本書紀の編纂者たちが後か
ら、元々の地名にこじつけたものであるのは明白だ。
■魏志倭人伝にいう「末廬国」は、現在の佐賀県唐津市を中心とした地域であるとする。この地域からは過去、豊富な
副葬品を持った遺跡が多く発掘されており、それらの遺跡の年代変遷により、末廬国の都がそれぞれの遺跡を中心とし
た地区に移っていったと考えられている。末盧国には、日本の稲作発祥の地、或いは日本農業の発祥の地とも言われる
「菜畑遺跡」があり、既に縄文末期から水田を営んでいたことはよく知られている。実際に舟で壱岐から渡ってきた印
象で言えば、松浦半島突端の「呼子(よぶこ)」やその沿岸は、切り立った崖でにわかには近づきがたい。それよりも
もっと内海へ入ってきて、唐津や虹ノ松原あたりに上陸したほうがはるかに楽だろう。もっとも、1,2世紀頃の唐津
の海岸がどういう地形だったのかはまだまだ検証が必要である。いずれにしても、菜畑から始まった縄文人・弥生人達
の営みは、葉山尻支石墓群、桜馬場遺跡、柏崎遺跡群、宇木遺跡群、などと変遷し、邪馬台国時代の古墳ともいわれ
る「久里双水古墳」に繋がっていく。
■弥生時代初めから中期にかけての、領域内の中心的な場所で国王の居所の侯補となれるような遺跡は、福岡県や佐賀
県など北九州を中心に数多く発見されている。福岡県では前原市三雲遺跡、福岡市吉武高木遺跡、春日市須玖遺跡、飯
塚市立岩遺跡、甘木市平塚川添遺跡、そして、佐賀県唐津市では、宇木汲田遺跡や桜馬場遺跡、柏崎遺跡などがその代
表例である。「使者や通訳が往来」しているという記録からみて、中国とこれらの国々の情勢は、お互いに刻々と把握
されていたとみてよい。佐賀県神埼郡神埼町と三田川町にまたがる「吉野ケ里遺跡」も忘れてはなるまい。時代が卑弥
呼の時代とは異なるとはされるが、あれだけの領域をもった国である。当然魏にも知られていたと見て良く、ひょっと
したら邪馬台国である可能性も完全にはぬぐいきれないと思う。
■伊都国の記述はそれまでと異なる点がいくつかある。まず、「東南」と方位があり、「陸行」している。末廬国には
なかった官名があり、それは、対馬国・一大国とは異なる。またなんと読むのかもはっきりしない。「代々王がいる。」
「女王に従属している。」「帯方郡の使者が常駐している。」これらは、これまでの大雑把な記述からすればかなり詳
細な情報といえる。
末廬から糸島地方は東にあたり、「陸行する」事を考えると、末盧国から伊都国へは水行では行けないということを意
味しており、伊都国は内陸地にあった国であるという説もある。つまり現在の糸島地方(前原市を中心とする旧糸島郡
・福岡市西部)は、末廬から東南ではなく、海路によってもいけるではないかと言うのだ。また唐津と前原では長里説
(200km)でも短里説(50km)でも五百里にはほど遠いとする。(唐津-前原間は約27km)。しかし、東
南には「イト」と呼ぶ地方はないし、古名にもない。さらに、見てきたように倭人伝の里数がかなり大雑把であること
を考えれば、伊都国は糸島地方としていいのではないかと思う。陸行については、伊都国から更に内陸部へ向かうこと
を考えれば、ここらから(末廬)陸上を行ったと解釈しても特に問題はないように思う。旧糸島郡は、前原町のあった
南側地域を怡土郡、北側地域を志摩郡といったが、明治29年合併して糸島郡となり、さらに平成4年(だったかな?)
市制を敷いて前原市となった。この前原市にある、「三雲、井原、平原付近」が伊都国に比定されている。この地域に
は標高416mの高祖山があり、456年から768年、大和朝廷の命によって吉備真備が対新羅戦争のために怡土城
を築いたことで知られている。
■「官は爾支。副は泄謨觚.柄渠觚。」というこの官名については不詳な部分が多い。「爾支」は「ニキ、ジキ、ニギ」な
どと呼ばれ、「泄謨觚」は「シマコ、セマコ、セモコ、イモコ」など、「柄渠觚」は「ヒココ、ヘクコ、ヒホコ」などと、注釈
されるが、その他にも色々に読め、後の日本語に対応しているようなものは見あたらない。「彦」や「妹子」などの「子」と
も関連するような気もするが、実態は不明である。
■壱岐から千余里で到達する範囲は、西は長崎県の五島列島から、東は福岡県の宗像郡あたりまでの任意の地点が比定
可能であるが、しかしそうなると後に続く伊都国の比定地との整合性がとれなくなってくる。末盧国をどこに比定する
は、従来の通説は、現在の佐賀県東松浦郡.西松浦郡.北松浦郡一帯であり、松浦半島の北端の呼子港と唐津説に分か
れている。勿論この場合、見てきたように里数が合わないので、外にも神湊説(宗像)、福岡説、佐世保港説、西彼杵
(にしそのぎ)半島説、伊万里港説、前原市の「三雲、井原、平原付近」説等々がある。しかしながら、末盧国=松浦
半島唐津市説が距離的にも直線最短コ-スであるし、「マツラ、マツロ」と「マツウラ」との音訳比定を考えれば、こ
の地が末廬国である確立は高いと思われる。里程が合わないという欠点はあるが、やはり末廬国は松浦半島周辺(特に
唐津市附近)なのであろうと思われる。
■マツラはマヅラに通音し、はじめ末羅であったが、のちに松浦の字をあててマツラと呼ぶようになった。日本書紀巻
第九、神功皇后摂政前紀仲哀天皇九年三月ー四月の条に「因りて竿を挙げて、乃ち細鱗魚を獲つ。時に皇后の曰はく、
梅豆邏(めづら)國と曰ふ。今、松浦と謂ふは訛れるなり」とある。しかしこの記事は、日本書紀の編纂者たちが後か
ら、元々の地名にこじつけたものであるのは明白だ。
■魏志倭人伝にいう「末廬国」は、現在の佐賀県唐津市を中心とした地域であるとする。この地域からは過去、豊富な
副葬品を持った遺跡が多く発掘されており、それらの遺跡の年代変遷により、末廬国の都がそれぞれの遺跡を中心とし
た地区に移っていったと考えられている。末盧国には、日本の稲作発祥の地、或いは日本農業の発祥の地とも言われる
「菜畑遺跡」があり、既に縄文末期から水田を営んでいたことはよく知られている。実際に舟で壱岐から渡ってきた印
象で言えば、松浦半島突端の「呼子(よぶこ)」やその沿岸は、切り立った崖でにわかには近づきがたい。それよりも
もっと内海へ入ってきて、唐津や虹ノ松原あたりに上陸したほうがはるかに楽だろう。もっとも、1,2世紀頃の唐津
の海岸がどういう地形だったのかはまだまだ検証が必要である。いずれにしても、菜畑から始まった縄文人・弥生人達
の営みは、葉山尻支石墓群、桜馬場遺跡、柏崎遺跡群、宇木遺跡群、などと変遷し、邪馬台国時代の古墳ともいわれ
る「久里双水古墳」に繋がっていく。
■弥生時代初めから中期にかけての、領域内の中心的な場所で国王の居所の侯補となれるような遺跡は、福岡県や佐賀
県など北九州を中心に数多く発見されている。福岡県では前原市三雲遺跡、福岡市吉武高木遺跡、春日市須玖遺跡、飯
塚市立岩遺跡、甘木市平塚川添遺跡、そして、佐賀県唐津市では、宇木汲田遺跡や桜馬場遺跡、柏崎遺跡などがその代
表例である。「使者や通訳が往来」しているという記録からみて、中国とこれらの国々の情勢は、お互いに刻々と把握
されていたとみてよい。佐賀県神埼郡神埼町と三田川町にまたがる「吉野ケ里遺跡」も忘れてはなるまい。時代が卑弥
呼の時代とは異なるとはされるが、あれだけの領域をもった国である。当然魏にも知られていたと見て良く、ひょっと
したら邪馬台国である可能性も完全にはぬぐいきれないと思う。
■伊都国の記述はそれまでと異なる点がいくつかある。まず、「東南」と方位があり、「陸行」している。末廬国には
なかった官名があり、それは、対馬国・一大国とは異なる。またなんと読むのかもはっきりしない。「代々王がいる。」
「女王に従属している。」「帯方郡の使者が常駐している。」これらは、これまでの大雑把な記述からすればかなり詳
細な情報といえる。
末廬から糸島地方は東にあたり、「陸行する」事を考えると、末盧国から伊都国へは水行では行けないということを意
味しており、伊都国は内陸地にあった国であるという説もある。つまり現在の糸島地方(前原市を中心とする旧糸島郡
・福岡市西部)は、末廬から東南ではなく、海路によってもいけるではないかと言うのだ。また唐津と前原では長里説
(200km)でも短里説(50km)でも五百里にはほど遠いとする。(唐津-前原間は約27km)。しかし、東
南には「イト」と呼ぶ地方はないし、古名にもない。さらに、見てきたように倭人伝の里数がかなり大雑把であること
を考えれば、伊都国は糸島地方としていいのではないかと思う。陸行については、伊都国から更に内陸部へ向かうこと
を考えれば、ここらから(末廬)陸上を行ったと解釈しても特に問題はないように思う。旧糸島郡は、前原町のあった
南側地域を怡土郡、北側地域を志摩郡といったが、明治29年合併して糸島郡となり、さらに平成4年(だったかな?)
市制を敷いて前原市となった。この前原市にある、「三雲、井原、平原付近」が伊都国に比定されている。この地域に
は標高416mの高祖山があり、456年から768年、大和朝廷の命によって吉備真備が対新羅戦争のために怡土城
を築いたことで知られている。
■「官は爾支。副は泄謨觚.柄渠觚。」というこの官名については不詳な部分が多い。「爾支」は「ニキ、ジキ、ニギ」な
どと呼ばれ、「泄謨觚」は「シマコ、セマコ、セモコ、イモコ」など、「柄渠觚」は「ヒココ、ヘクコ、ヒホコ」などと、注釈
されるが、その他にも色々に読め、後の日本語に対応しているようなものは見あたらない。「彦」や「妹子」などの「子」と
も関連するような気もするが、実態は不明である。
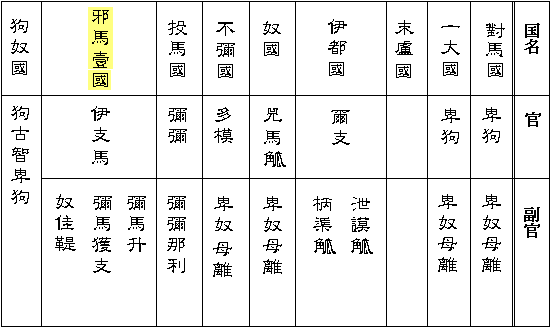 ■しかしながらその他の多くの官名は、日本の「古事記」「日本書紀」の神代の巻に現れる神名などと一致するものが
多いのは注目される。不彌國の官「多模」は、「万葉仮名の読み方」で正確に「たま」と読め、古事記には「玉の祖の
命(たまのおやのみこと)」「布刀玉の命(ふとだまのみこと)」「宇迦の御魂の神(うかのみたまのかみ)」など列
挙に暇がないほど現れるし、投馬國の官「彌彌」はこれも上古音で「みみ」と呼ぶことができ、「天の忍穂耳の命(あ
めのおしほみみのみこと)」「多芸志美美の命(たげしみみのみこと)」「建沼河耳の命(たけぬなかはみみのみこと)」
「神沼河耳の命(かむぬなかはみみのみこと)」など、「みみ」を含む神名・人名はかなり出現する。「卑狗」を「ひ
こ」と呼ぶことは定説で、これ又記紀には相当出現するし、「卑奴母離」を「ひなもり」と呼んで後世の「夷守」にあ
てる事にも異論はない。安本美典氏は、「爾支」を「ニギ」と呼んで「邇邇芸の尊(ににぎのみこと)」「邇芸速日の命
(にぎはやひのみこと)」の邇芸にあたるとしている。また氏も「泄謨觚.柄渠觚」、及び、奴国の官名「兄(当て字)
馬觚」の呼び方は相当難しいとしながらも、「泄謨觚・兄馬觚」を「しまこ」、「柄渠觚」を「ひここ」或いは「ほこ
こ」の可能性が高いとしている。(「倭人語の解読:平成15年6月1日・勉誠出版発行」)
■伊都国の戸数「千余戸」は、この国の重要度からみて少なすぎるのではないかという説がある。「戸万余」の間違い
ではないかと言うのだが、魏の使者が常駐したり、代々王がいたり、という国の規模からすれば確かに少ないかも知れ
ない。しかし王が居ればこそ、ここに住める一般人は限られていたと想像する事もできる。「王」の存在が明らかなのは、
この伊都国と邪馬台国と狗奴国の三国だけである。「世々王有るも、皆女王国に統属す。」とあるように、伊都国は古
くから卑弥呼を支えていた主要国と見ていいだろう。だからこそ「郡使が往来するとき常に駐まる所。」という邪馬台
国連合国家の中で、外交的に重要な役割と地位を占めていたと考えられる。
■倭人伝には、伊都国以前は方角、距離、国名と順に記されているのに対し、伊都国以降は方角、国名、距離の順に記
載されており、距離と国名の順序が入れ替わっている。このことを指摘したのは榎一雄氏であるが、その提唱の要旨は、
「倭人伝は、伊都国まで連続に末盧国、伊都国、奴国と読み進む形式で記されているが、伊都国以降は、奴国、不弥国、
投馬国、邪馬台国と、伊都国を起点として読み進められるべきだ。」というものである。これは「放射説」と呼ばれ、
あたらしい倭人伝の解釈として脚光を浴びた。邪馬台国に次ぐ重要な地位を占めている(と思われる)伊都国から、魏
使は様々な国を訪問したという考えに基づく。これは一考を要していい説であろう。
■【魏略曰】
「又渡海千餘里、至末廬國、人善捕魚、能浮沒水取之。東南五百里、到伊都國。戸万餘。置官曰爾支、副曰曳渓觚・柄
渠觚。皆統屬女王也。」
--------------------------------------------------------------------------------
東南至奴國百里。官曰ji[冠凹脚儿]馬觚、副曰卑奴母離。有二萬餘戸。東行至不彌國百里。官曰多模、副曰卑奴母離。
有千餘家。南至投馬國水行二十日、官曰彌彌、副曰彌彌那利、可五萬餘戸。南至邪馬壹國、女王之所都、水行十日、陸
行一月。官有伊支馬、次曰彌馬升、次曰彌馬獲支、次曰奴佳[革是]、可七萬餘戸。
東南して奴国に至る。官は兒馬觚といい、副は卑奴母離という。2万余戸あり。東行不弥国に至る。百里。官を多模と
いい、副を卑奴母離という。千余の家あり。南、投馬国に至る。水行二十日。官を彌彌といい、副を彌彌那利という。
五万余戸ばかりあり。南、邪馬台国に至る。女王の郡する所なり。水行十日、陸行一月。官に伊支馬あり。次を彌馬升
といい、次は彌馬獲支といい、次は奴佳韃という。7万余戸ばかりあり。
そこから東南の方角へ行くと奴国(今の博多)に至る。距離は百里である。長官をジ馬觚といい、副官を卑奴毋離とい
う。二万余戸がある。東の方角へ行くと、不弥国に至る。百里である。長官を多模といい、副官を卑奴毋離という。
千余戸がある。南へ行くと、投馬国に至る。水行(一海を渡ると区別している事から、この表現は川を行くものだ、と
の説がある。)で二十日かかる。長官を弥弥といい、副官を弥弥那利という。五万余戸ばかりの人口である。南へ行く
と、邪馬台国に到達する。女王の都がある所である、水行十日(と/又はの二説あり。)陸行一月である。長官を伊支
馬といい、次官を弥馬升とい い、次官を弥馬獲支といい、次官を奴佳タイという。七万余戸ばかりの人口である。
■福岡県春日市。福岡市の東南に位置し、春日丘陵と呼ばれる福岡平野の南部丘陵を形成している。この地方は古くか
ら古代の墳墓・遺跡が発見されており、中でも青銅器生産関連の遺物が多いことで注目されていた。記録の最初は江戸
時代にさかのぼる。福岡藩(黒田藩)の国学者であった青柳種信(1766~1835:明和3年~天保6年)が編纂した「筑前
国続風土記拾遺」に、広形銅矛の鋳型の記事が見える。「筑前国那珂須玖村熊野神社神殿所納銅鉾型」というのがそれ
で、これは現在も熊野神社が所蔵しているが、種信が書き記した時点で既に熊野神社が保有していたことを考えると、
既にその前に掘り出されていたはずである。又、熊野神社には「王墓の上石」と呼ばれる平板の石板も残されていたが、
これは、明治時代に家を建てるのにじゃまだというので動かしたところ、下に墳墓があり、中から鏡(前漢鏡?)が30
面以上、銅剣・銅鉾・銅戈などの青銅器が8本以上、ガラスの壁(へき)やガラスの勾玉などが多数出土したと言う。
これらの副葬品は既に散逸してしまっているが、上石だけは転々と場所を代え、熊野神社に残っていたもの。
現在は「奴国の丘歴史公園」内に移転されている。
■「須玖岡本遺跡群」と呼ばれる、春日丘陵に点在する古代遺跡があるあたりは福岡市のベッドタウンであり、古くか
ら住居がひしめいている。その為これらの住居の下にも相当の遺跡が眠っていることが想像できるが、現時点ではどう
しようもない。春日市教育委員会では、どんな小さな場所でもいいから立て替えるときには必ず調査を行わせてほしい
と市民に呼びかけ、市民もこれに答えている。勿論調査後遺跡は再び埋め戻され、本来の住宅が建設される。かっての
王墓の跡も今は埋め戻され、わずかに案内板が立てられているだけで、上には現代人が住んでいる。
■「岡本遺跡」では今から2000年前(弥生時代中期)の甕棺墓・木棺墓・土壙墓・祭祀遺構・住居跡が見つかっている。
又遺跡公園内には、奴国王の墓の上を覆っていたという大石を熊野神社から移設しているが、この墓については、同じ
く公園内に創設された「歴史資料館」に解説がある。資料館にはこの他、須玖岡本遺跡群から発掘された遺物が多数展
示されている。この遺跡がほんとに「奴国」の中心地であったかどうか、又「王墓」とされている遺構もほんとに王の
ものかどうかについては異論もある。しかし現在までの所、奴国に相当すると思われる地域(福岡市から春日市、大野
城市、筑紫野市あたり)からは、この遺跡群を上回る規模の遺跡は発見されていないのだ。従って今の所、「奴国の都」
の最有力候補地と言ったほうが正確かもしれない。
■全国で初めてガラス製品の製作工房跡がわかったのも、この春日丘陵の須玖五反田遺跡である。ガラスの勾玉の鋳型
が出土した遺跡は、これまでに9つが知られている。大阪府茨木市・東奈良遺跡、山口県菊川町・下七見遺跡の2ケ所
の他は、全てこの春日丘陵とその周辺である。ガラス製品の製作は弥生中期に始まると考えられているが、中期の鋳型
が出土する所では具体的な製作を示す他の遺物や遺構がわかっていない。須玖五反田遺跡では、勾玉鋳型が複数個、坩
堝(るつぼ)、勾玉の未製品などが出土して製作を裏付けているが、時期は後期後半と見られている。
須玖五反田遺跡を発掘調査した春日市教育委員会の吉田佳広氏は、「溶解温度の低いガラスは青銅に比べて遙かに鋳造
し易いが、その製作に関して専門知識と熟練が必要な事は青銅器と変わりなく、原料の入手や製造技術にも共通する点
が多い。青銅器の工人の中でガラスを扱う技術を習得した者は、青銅器工房の一角において、さまざまな青銅器ととも
にガラス製品の製作を行っていたものと思われる。」と述べ、ガラス製品の製作が推測される遺跡では、同時に青銅器
生産に関する遺物も伴っている事を指摘している。
■さてついに邪馬台国へ到着するが、周知のようにその位置は未だ判明していない。不弥國から南へ水行で二十日かか
ると投馬國へ到着し、さらに南へ水行十日、陸行一月で「邪馬台国」と言うことになる。奴國が博多湾岸から春日市の
あたりだと想定すると、東の不弥國は、従来通り宇美町・飯塚市・嘉穂郡あたりになり、その南は三井郡から甘木・朝
倉地方、或いは浮羽郡・久留米市を含むエリアが考えられるが、水行の意味が不明だし、川を降っても(どの河かがま
た問題になるが、宝満川あたりか。)1日で下ってしまう。20日もかからない。有明海へ出て、更に筑後川を遡り甘
木・朝倉へ行くことはできるが、これとて4,5日もかからないだろう。さらに、その投馬國から水行十日、陸行一月
と言うことになるともうお手上げである。大阪風に言うと「頭湧くねぇ」という事になる。日数日程を度外視して、不
弥国から南へ南へと下ってくれば以下の図のようになるのだが、ここまで日数・行程を無視するには当然それなりの論
理が必要になる。
■しかしながらその他の多くの官名は、日本の「古事記」「日本書紀」の神代の巻に現れる神名などと一致するものが
多いのは注目される。不彌國の官「多模」は、「万葉仮名の読み方」で正確に「たま」と読め、古事記には「玉の祖の
命(たまのおやのみこと)」「布刀玉の命(ふとだまのみこと)」「宇迦の御魂の神(うかのみたまのかみ)」など列
挙に暇がないほど現れるし、投馬國の官「彌彌」はこれも上古音で「みみ」と呼ぶことができ、「天の忍穂耳の命(あ
めのおしほみみのみこと)」「多芸志美美の命(たげしみみのみこと)」「建沼河耳の命(たけぬなかはみみのみこと)」
「神沼河耳の命(かむぬなかはみみのみこと)」など、「みみ」を含む神名・人名はかなり出現する。「卑狗」を「ひ
こ」と呼ぶことは定説で、これ又記紀には相当出現するし、「卑奴母離」を「ひなもり」と呼んで後世の「夷守」にあ
てる事にも異論はない。安本美典氏は、「爾支」を「ニギ」と呼んで「邇邇芸の尊(ににぎのみこと)」「邇芸速日の命
(にぎはやひのみこと)」の邇芸にあたるとしている。また氏も「泄謨觚.柄渠觚」、及び、奴国の官名「兄(当て字)
馬觚」の呼び方は相当難しいとしながらも、「泄謨觚・兄馬觚」を「しまこ」、「柄渠觚」を「ひここ」或いは「ほこ
こ」の可能性が高いとしている。(「倭人語の解読:平成15年6月1日・勉誠出版発行」)
■伊都国の戸数「千余戸」は、この国の重要度からみて少なすぎるのではないかという説がある。「戸万余」の間違い
ではないかと言うのだが、魏の使者が常駐したり、代々王がいたり、という国の規模からすれば確かに少ないかも知れ
ない。しかし王が居ればこそ、ここに住める一般人は限られていたと想像する事もできる。「王」の存在が明らかなのは、
この伊都国と邪馬台国と狗奴国の三国だけである。「世々王有るも、皆女王国に統属す。」とあるように、伊都国は古
くから卑弥呼を支えていた主要国と見ていいだろう。だからこそ「郡使が往来するとき常に駐まる所。」という邪馬台
国連合国家の中で、外交的に重要な役割と地位を占めていたと考えられる。
■倭人伝には、伊都国以前は方角、距離、国名と順に記されているのに対し、伊都国以降は方角、国名、距離の順に記
載されており、距離と国名の順序が入れ替わっている。このことを指摘したのは榎一雄氏であるが、その提唱の要旨は、
「倭人伝は、伊都国まで連続に末盧国、伊都国、奴国と読み進む形式で記されているが、伊都国以降は、奴国、不弥国、
投馬国、邪馬台国と、伊都国を起点として読み進められるべきだ。」というものである。これは「放射説」と呼ばれ、
あたらしい倭人伝の解釈として脚光を浴びた。邪馬台国に次ぐ重要な地位を占めている(と思われる)伊都国から、魏
使は様々な国を訪問したという考えに基づく。これは一考を要していい説であろう。
■【魏略曰】
「又渡海千餘里、至末廬國、人善捕魚、能浮沒水取之。東南五百里、到伊都國。戸万餘。置官曰爾支、副曰曳渓觚・柄
渠觚。皆統屬女王也。」
--------------------------------------------------------------------------------
東南至奴國百里。官曰ji[冠凹脚儿]馬觚、副曰卑奴母離。有二萬餘戸。東行至不彌國百里。官曰多模、副曰卑奴母離。
有千餘家。南至投馬國水行二十日、官曰彌彌、副曰彌彌那利、可五萬餘戸。南至邪馬壹國、女王之所都、水行十日、陸
行一月。官有伊支馬、次曰彌馬升、次曰彌馬獲支、次曰奴佳[革是]、可七萬餘戸。
東南して奴国に至る。官は兒馬觚といい、副は卑奴母離という。2万余戸あり。東行不弥国に至る。百里。官を多模と
いい、副を卑奴母離という。千余の家あり。南、投馬国に至る。水行二十日。官を彌彌といい、副を彌彌那利という。
五万余戸ばかりあり。南、邪馬台国に至る。女王の郡する所なり。水行十日、陸行一月。官に伊支馬あり。次を彌馬升
といい、次は彌馬獲支といい、次は奴佳韃という。7万余戸ばかりあり。
そこから東南の方角へ行くと奴国(今の博多)に至る。距離は百里である。長官をジ馬觚といい、副官を卑奴毋離とい
う。二万余戸がある。東の方角へ行くと、不弥国に至る。百里である。長官を多模といい、副官を卑奴毋離という。
千余戸がある。南へ行くと、投馬国に至る。水行(一海を渡ると区別している事から、この表現は川を行くものだ、と
の説がある。)で二十日かかる。長官を弥弥といい、副官を弥弥那利という。五万余戸ばかりの人口である。南へ行く
と、邪馬台国に到達する。女王の都がある所である、水行十日(と/又はの二説あり。)陸行一月である。長官を伊支
馬といい、次官を弥馬升とい い、次官を弥馬獲支といい、次官を奴佳タイという。七万余戸ばかりの人口である。
■福岡県春日市。福岡市の東南に位置し、春日丘陵と呼ばれる福岡平野の南部丘陵を形成している。この地方は古くか
ら古代の墳墓・遺跡が発見されており、中でも青銅器生産関連の遺物が多いことで注目されていた。記録の最初は江戸
時代にさかのぼる。福岡藩(黒田藩)の国学者であった青柳種信(1766~1835:明和3年~天保6年)が編纂した「筑前
国続風土記拾遺」に、広形銅矛の鋳型の記事が見える。「筑前国那珂須玖村熊野神社神殿所納銅鉾型」というのがそれ
で、これは現在も熊野神社が所蔵しているが、種信が書き記した時点で既に熊野神社が保有していたことを考えると、
既にその前に掘り出されていたはずである。又、熊野神社には「王墓の上石」と呼ばれる平板の石板も残されていたが、
これは、明治時代に家を建てるのにじゃまだというので動かしたところ、下に墳墓があり、中から鏡(前漢鏡?)が30
面以上、銅剣・銅鉾・銅戈などの青銅器が8本以上、ガラスの壁(へき)やガラスの勾玉などが多数出土したと言う。
これらの副葬品は既に散逸してしまっているが、上石だけは転々と場所を代え、熊野神社に残っていたもの。
現在は「奴国の丘歴史公園」内に移転されている。
■「須玖岡本遺跡群」と呼ばれる、春日丘陵に点在する古代遺跡があるあたりは福岡市のベッドタウンであり、古くか
ら住居がひしめいている。その為これらの住居の下にも相当の遺跡が眠っていることが想像できるが、現時点ではどう
しようもない。春日市教育委員会では、どんな小さな場所でもいいから立て替えるときには必ず調査を行わせてほしい
と市民に呼びかけ、市民もこれに答えている。勿論調査後遺跡は再び埋め戻され、本来の住宅が建設される。かっての
王墓の跡も今は埋め戻され、わずかに案内板が立てられているだけで、上には現代人が住んでいる。
■「岡本遺跡」では今から2000年前(弥生時代中期)の甕棺墓・木棺墓・土壙墓・祭祀遺構・住居跡が見つかっている。
又遺跡公園内には、奴国王の墓の上を覆っていたという大石を熊野神社から移設しているが、この墓については、同じ
く公園内に創設された「歴史資料館」に解説がある。資料館にはこの他、須玖岡本遺跡群から発掘された遺物が多数展
示されている。この遺跡がほんとに「奴国」の中心地であったかどうか、又「王墓」とされている遺構もほんとに王の
ものかどうかについては異論もある。しかし現在までの所、奴国に相当すると思われる地域(福岡市から春日市、大野
城市、筑紫野市あたり)からは、この遺跡群を上回る規模の遺跡は発見されていないのだ。従って今の所、「奴国の都」
の最有力候補地と言ったほうが正確かもしれない。
■全国で初めてガラス製品の製作工房跡がわかったのも、この春日丘陵の須玖五反田遺跡である。ガラスの勾玉の鋳型
が出土した遺跡は、これまでに9つが知られている。大阪府茨木市・東奈良遺跡、山口県菊川町・下七見遺跡の2ケ所
の他は、全てこの春日丘陵とその周辺である。ガラス製品の製作は弥生中期に始まると考えられているが、中期の鋳型
が出土する所では具体的な製作を示す他の遺物や遺構がわかっていない。須玖五反田遺跡では、勾玉鋳型が複数個、坩
堝(るつぼ)、勾玉の未製品などが出土して製作を裏付けているが、時期は後期後半と見られている。
須玖五反田遺跡を発掘調査した春日市教育委員会の吉田佳広氏は、「溶解温度の低いガラスは青銅に比べて遙かに鋳造
し易いが、その製作に関して専門知識と熟練が必要な事は青銅器と変わりなく、原料の入手や製造技術にも共通する点
が多い。青銅器の工人の中でガラスを扱う技術を習得した者は、青銅器工房の一角において、さまざまな青銅器ととも
にガラス製品の製作を行っていたものと思われる。」と述べ、ガラス製品の製作が推測される遺跡では、同時に青銅器
生産に関する遺物も伴っている事を指摘している。
■さてついに邪馬台国へ到着するが、周知のようにその位置は未だ判明していない。不弥國から南へ水行で二十日かか
ると投馬國へ到着し、さらに南へ水行十日、陸行一月で「邪馬台国」と言うことになる。奴國が博多湾岸から春日市の
あたりだと想定すると、東の不弥國は、従来通り宇美町・飯塚市・嘉穂郡あたりになり、その南は三井郡から甘木・朝
倉地方、或いは浮羽郡・久留米市を含むエリアが考えられるが、水行の意味が不明だし、川を降っても(どの河かがま
た問題になるが、宝満川あたりか。)1日で下ってしまう。20日もかからない。有明海へ出て、更に筑後川を遡り甘
木・朝倉へ行くことはできるが、これとて4,5日もかからないだろう。さらに、その投馬國から水行十日、陸行一月
と言うことになるともうお手上げである。大阪風に言うと「頭湧くねぇ」という事になる。日数日程を度外視して、不
弥国から南へ南へと下ってくれば以下の図のようになるのだが、ここまで日数・行程を無視するには当然それなりの論
理が必要になる。
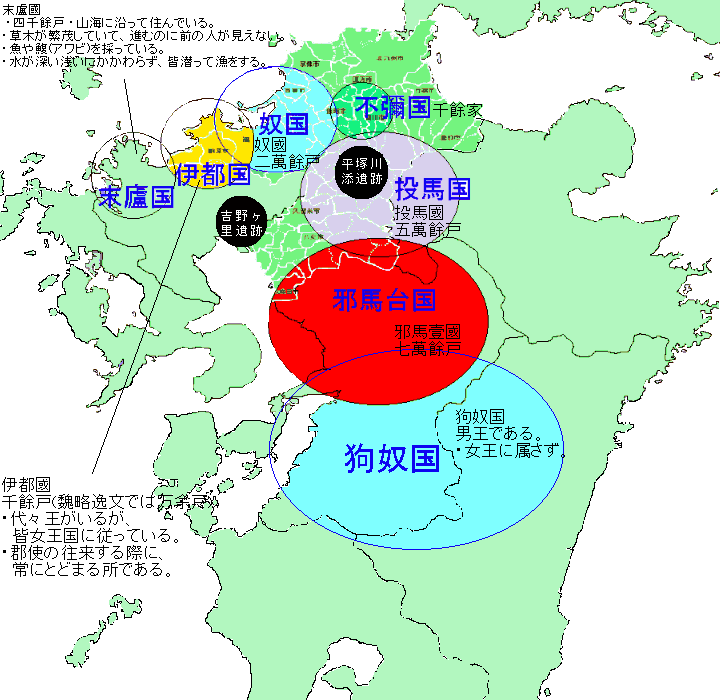 ■上の図は、倭人伝の「倭国」描写が九州島に限られているという前提に立てば、非常にスッキリした位置に納まって
いるようにも思えるが、日程を無視しているし、陸行や水行などの手段も全く考慮していない。
--------------------------------------------------------------------------------
自女王國以北、其戸數道里可得略載、其餘旁國遠絶、不可得詳。次有斯馬國、次有已百支國、次有伊邪國、次有都支國、
次有彌奴國、次有好古都國、次有不呼國、次有姐奴國、次有對蘇國、次有蘇奴國、次有呼邑國、次有華奴蘇奴國、次有
鬼國、次有爲吾國、次有鬼奴國、次有邪馬國、次有躬臣國、次有巴利國、次有支惟國、次有烏奴國、次有奴國、此女王
境界所盡。其南有狗奴國、男子爲王、其官有狗古智卑狗、不屬女王。自郡至女王國萬二千餘里。
女王国より以北はその戸数・道里は得て略載すべきも、その余の旁国は遠絶にして詳らかにすることを得べからず。次
に斯馬国あり。次に己百支国あり。次に伊邪国あり。次に郡支国あり。次に彌奴国あり。次に好古都国あり。次に不呼
国あり。次に姐奴国あり。次に対蘇国あり。次に蘇奴国あり。次に呼邑国あり。次に華奴蘇奴国あり。次に鬼国あり。
次に為吾国あり。次に鬼奴国あり。次に邪馬国あり。次に躬臣国あり。次に巴利国あり。次に支惟国あり。次に烏奴国
あり。次に奴国あり。これ女王に境界の尽くる所なり。その南に狗奴国あり。男子を王となす。その官に狗古智卑狗あ
り。女王に属せず。郡より女王国に至ること万二千余里。
女王国より北の方角についてはその戸数・道里は記載できるが、その他の周辺の國は遠くて交渉が無く、詳細は不明で
ある。次に斯馬国があり、次に已百支国あり、次に伊邪国あり、次に都支国あり、次に弥奴 国あり、次に好古都国あり、
次に不呼国あり、次に姐奴国あり、次に対蘇国あり、次に蘇奴国あり、次に呼邑国あり、次に華奴蘇奴国あり、次に鬼
国あり、次に為吾国あり、次に鬼奴国あり、次に邪馬国あり、次に躬臣国あり、次に巴利国あり、次に支惟国あり、次
に烏奴国あり、次に奴国あり。これが女王の(権力の)尽きる所である。その南に狗奴国があり(今の熊本か?)、男
子の王がいる。その長官は狗古智卑狗であり、(この國は)女王國に隷属していない。帯方郡より女王国に至るまでは
一万二千余里である。
■この部分はもっぱら魚拳の「魏略」を参考にして書かれており、三国志は魏略を多く引用していると言われる。
ここにいう「女王国より以北はその戸数・道里は得て略載すべきも、その余の旁国は遠絶にして詳らかにすることを得
べからず。」という部分は注目に値する。これまで述べてきた戸数・道里が略載であると明言している。つまり戸数・
道里は確実なものではないと陳壽自身認めている事になる。以下の余旁国二十一国についても、学者によってはまるっ
きり架空のもので、いちいち検討するのは無駄であるとして、全く言及しない人もいるくらいだ。二十一国を順に書き
出すと「 1.斯馬國 2.已百支國 3.伊邪國 4.都支國 5.彌奴國 6.好古都國 7.不呼國 8.姐奴國 9.對
蘇國 10.蘇奴國 11.呼邑國 12.華奴蘇奴國 13.鬼國 14.爲吾國 15.鬼奴國 16.邪馬國 17.躬
臣國 18.巴利國 19.支惟國 20.烏奴國 21.奴國」 となってまた奴國で終わっている。
■ここで倭人伝に登場する国々とその行程をまとめてみると以下のようになる。
国 方角 距離 特記
========= ==== ============= ======================================
狗邪韓国 東南 七千余里 ・帯方郡の東南 ・海岸をめぐりて水行。
・韓国を経て、あるいは南あるいは東。
対馬国 ? 千余里 ・始めて一海を渡る。
一大国 南 千余里 ・瀚海を渡る。
末盧国 ? 千余里 ・一海を渡る。
伊都国 東南 陸行五百里
奴国 東南 百里
不彌国 東行 百里
投馬国 南 水行二十日
邪馬台国 南 水行十日陸行一月 ・帯方郡より女王国に至るに万二千余里。
余旁国 ? ? ・遠絶にして詳らかにするを得ず 二十一国。
狗奴国 南 ?
倭種の国 東 千余里 ・海を渡る。・女王国の東。
侏儒國 南 四千余里 ・倭種の国の南 ・女王国から四千余里・人長三四尺。
裸国・黒歯国 東南 船行一年 ・侏儒國の東南。
■これを解釈して、邪馬台国畿内説、九州説が論戦を重ねているのは周知のごとくであるが、その概略を図示すると概
ね以下のようになる。
■上の図は、倭人伝の「倭国」描写が九州島に限られているという前提に立てば、非常にスッキリした位置に納まって
いるようにも思えるが、日程を無視しているし、陸行や水行などの手段も全く考慮していない。
--------------------------------------------------------------------------------
自女王國以北、其戸數道里可得略載、其餘旁國遠絶、不可得詳。次有斯馬國、次有已百支國、次有伊邪國、次有都支國、
次有彌奴國、次有好古都國、次有不呼國、次有姐奴國、次有對蘇國、次有蘇奴國、次有呼邑國、次有華奴蘇奴國、次有
鬼國、次有爲吾國、次有鬼奴國、次有邪馬國、次有躬臣國、次有巴利國、次有支惟國、次有烏奴國、次有奴國、此女王
境界所盡。其南有狗奴國、男子爲王、其官有狗古智卑狗、不屬女王。自郡至女王國萬二千餘里。
女王国より以北はその戸数・道里は得て略載すべきも、その余の旁国は遠絶にして詳らかにすることを得べからず。次
に斯馬国あり。次に己百支国あり。次に伊邪国あり。次に郡支国あり。次に彌奴国あり。次に好古都国あり。次に不呼
国あり。次に姐奴国あり。次に対蘇国あり。次に蘇奴国あり。次に呼邑国あり。次に華奴蘇奴国あり。次に鬼国あり。
次に為吾国あり。次に鬼奴国あり。次に邪馬国あり。次に躬臣国あり。次に巴利国あり。次に支惟国あり。次に烏奴国
あり。次に奴国あり。これ女王に境界の尽くる所なり。その南に狗奴国あり。男子を王となす。その官に狗古智卑狗あ
り。女王に属せず。郡より女王国に至ること万二千余里。
女王国より北の方角についてはその戸数・道里は記載できるが、その他の周辺の國は遠くて交渉が無く、詳細は不明で
ある。次に斯馬国があり、次に已百支国あり、次に伊邪国あり、次に都支国あり、次に弥奴 国あり、次に好古都国あり、
次に不呼国あり、次に姐奴国あり、次に対蘇国あり、次に蘇奴国あり、次に呼邑国あり、次に華奴蘇奴国あり、次に鬼
国あり、次に為吾国あり、次に鬼奴国あり、次に邪馬国あり、次に躬臣国あり、次に巴利国あり、次に支惟国あり、次
に烏奴国あり、次に奴国あり。これが女王の(権力の)尽きる所である。その南に狗奴国があり(今の熊本か?)、男
子の王がいる。その長官は狗古智卑狗であり、(この國は)女王國に隷属していない。帯方郡より女王国に至るまでは
一万二千余里である。
■この部分はもっぱら魚拳の「魏略」を参考にして書かれており、三国志は魏略を多く引用していると言われる。
ここにいう「女王国より以北はその戸数・道里は得て略載すべきも、その余の旁国は遠絶にして詳らかにすることを得
べからず。」という部分は注目に値する。これまで述べてきた戸数・道里が略載であると明言している。つまり戸数・
道里は確実なものではないと陳壽自身認めている事になる。以下の余旁国二十一国についても、学者によってはまるっ
きり架空のもので、いちいち検討するのは無駄であるとして、全く言及しない人もいるくらいだ。二十一国を順に書き
出すと「 1.斯馬國 2.已百支國 3.伊邪國 4.都支國 5.彌奴國 6.好古都國 7.不呼國 8.姐奴國 9.對
蘇國 10.蘇奴國 11.呼邑國 12.華奴蘇奴國 13.鬼國 14.爲吾國 15.鬼奴國 16.邪馬國 17.躬
臣國 18.巴利國 19.支惟國 20.烏奴國 21.奴國」 となってまた奴國で終わっている。
■ここで倭人伝に登場する国々とその行程をまとめてみると以下のようになる。
国 方角 距離 特記
========= ==== ============= ======================================
狗邪韓国 東南 七千余里 ・帯方郡の東南 ・海岸をめぐりて水行。
・韓国を経て、あるいは南あるいは東。
対馬国 ? 千余里 ・始めて一海を渡る。
一大国 南 千余里 ・瀚海を渡る。
末盧国 ? 千余里 ・一海を渡る。
伊都国 東南 陸行五百里
奴国 東南 百里
不彌国 東行 百里
投馬国 南 水行二十日
邪馬台国 南 水行十日陸行一月 ・帯方郡より女王国に至るに万二千余里。
余旁国 ? ? ・遠絶にして詳らかにするを得ず 二十一国。
狗奴国 南 ?
倭種の国 東 千余里 ・海を渡る。・女王国の東。
侏儒國 南 四千余里 ・倭種の国の南 ・女王国から四千余里・人長三四尺。
裸国・黒歯国 東南 船行一年 ・侏儒國の東南。
■これを解釈して、邪馬台国畿内説、九州説が論戦を重ねているのは周知のごとくであるが、その概略を図示すると概
ね以下のようになる。
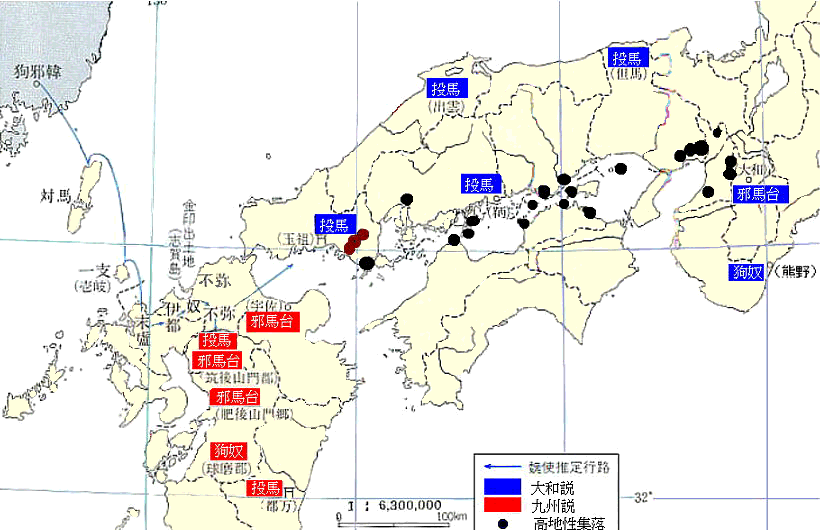
■ここにいう方角や日程や距離の情報はどこまでが正しいのだろうか?全部が正しく書いてあるとしたら、この記事か
らは今のところ邪馬台国は判明しないと言うことになる。「これはでたらめ、伝聞で書いている。」とか「一月は一日
の誤り。」などとどこかを無視しなければ「説」は成り立たないようになっている。ここがこの論争の実におもしろい
ところで、陳壽が計算して記録を残したとすれば、彼は天才的な推理作家の素養を持っていた事にもなる。
■いずれにしてもこの記事は、おおむね北九州の弥生時代中期の初めころの状況を記録したもののようであり、中国人
の目に「国」として認識された領域(その領域内に王が存在しその居所となる王都があるような)が、当時三十ばかり
あったという事を示している。そして、末廬国、伊都国、奴国などを見てもわかるように、当時の国々の領域は極めて
小さい。現在の市町村の領域が当時の国である。そして三十の国々は当然の事ながら北九州のエリア内にすっぽりと収
まってしまうのである。邪馬台国が近畿にあったとすると、それを取り巻く国々が三十というのはあまりに少なすぎる。
各地で発見される遺跡を見ても、この中国人の観点からすれば十分に国として認識されて良い領域は、北九州から近畿
までの間にごまんとある。魏志倭人伝には300くらいの国の名が記録されていないとおかしい。倭人伝が対象にして
いる「倭」の範囲は、韓国南部から北九州の範囲を指しているのは明らかだ。
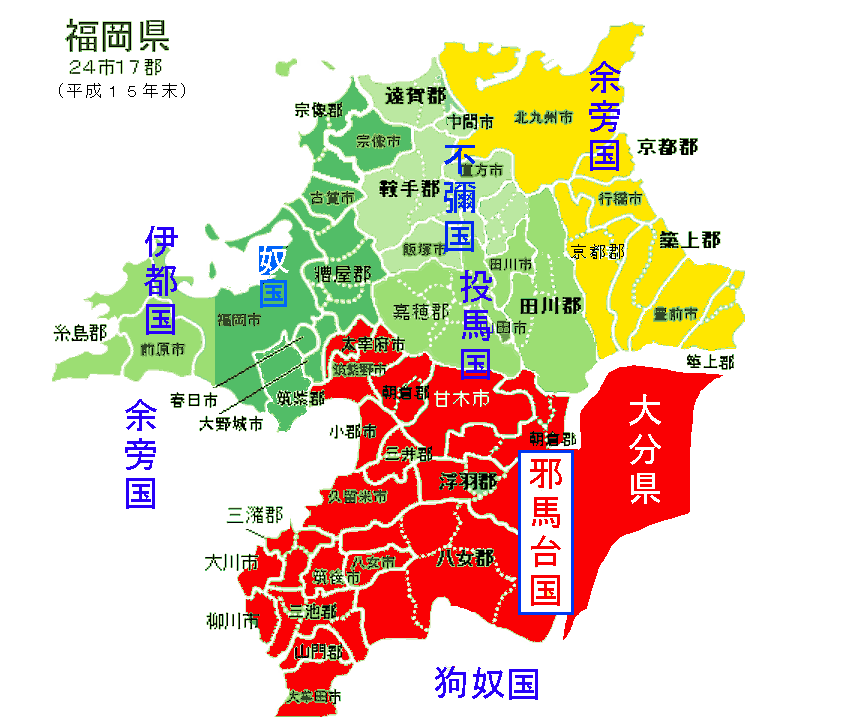
■私の考える邪馬台国の位置は概ね上図のようなものだったのではないかと思うが、その根拠についてはこの「本編」
の中で、明らかにしていきたいと思う。
 邪馬台国大研究・ホームページ / わちゃごなどう?/ 本編
邪馬台国大研究・ホームページ / わちゃごなどう?/ 本編
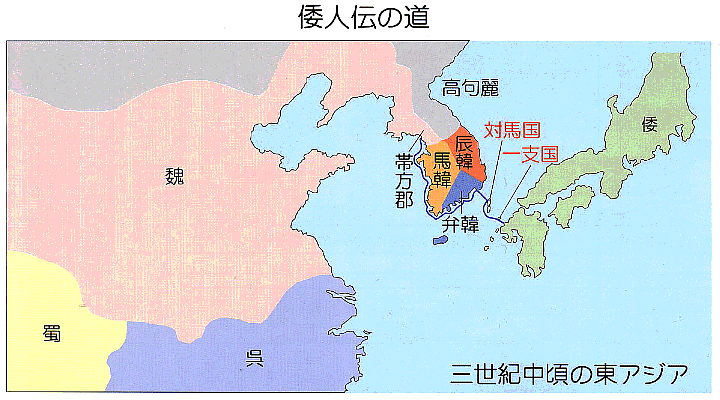
■壱岐から千余里で到達する範囲は、西は長崎県の五島列島から、東は福岡県の宗像郡あたりまでの任意の地点が比定 可能であるが、しかしそうなると後に続く伊都国の比定地との整合性がとれなくなってくる。末盧国をどこに比定する は、従来の通説は、現在の佐賀県東松浦郡.西松浦郡.北松浦郡一帯であり、松浦半島の北端の呼子港と唐津説に分か れている。勿論この場合、見てきたように里数が合わないので、外にも神湊説(宗像)、福岡説、佐世保港説、西彼杵 (にしそのぎ)半島説、伊万里港説、前原市の「三雲、井原、平原付近」説等々がある。しかしながら、末盧国=松浦 半島唐津市説が距離的にも直線最短コ-スであるし、「マツラ、マツロ」と「マツウラ」との音訳比定を考えれば、こ の地が末廬国である確立は高いと思われる。里程が合わないという欠点はあるが、やはり末廬国は松浦半島周辺(特に 唐津市附近)なのであろうと思われる。 ■マツラはマヅラに通音し、はじめ末羅であったが、のちに松浦の字をあててマツラと呼ぶようになった。日本書紀巻 第九、神功皇后摂政前紀仲哀天皇九年三月ー四月の条に「因りて竿を挙げて、乃ち細鱗魚を獲つ。時に皇后の曰はく、 梅豆邏(めづら)國と曰ふ。今、松浦と謂ふは訛れるなり」とある。しかしこの記事は、日本書紀の編纂者たちが後か ら、元々の地名にこじつけたものであるのは明白だ。 ■魏志倭人伝にいう「末廬国」は、現在の佐賀県唐津市を中心とした地域であるとする。この地域からは過去、豊富な 副葬品を持った遺跡が多く発掘されており、それらの遺跡の年代変遷により、末廬国の都がそれぞれの遺跡を中心とし た地区に移っていったと考えられている。末盧国には、日本の稲作発祥の地、或いは日本農業の発祥の地とも言われる 「菜畑遺跡」があり、既に縄文末期から水田を営んでいたことはよく知られている。実際に舟で壱岐から渡ってきた印 象で言えば、松浦半島突端の「呼子(よぶこ)」やその沿岸は、切り立った崖でにわかには近づきがたい。それよりも もっと内海へ入ってきて、唐津や虹ノ松原あたりに上陸したほうがはるかに楽だろう。もっとも、1,2世紀頃の唐津 の海岸がどういう地形だったのかはまだまだ検証が必要である。いずれにしても、菜畑から始まった縄文人・弥生人達 の営みは、葉山尻支石墓群、桜馬場遺跡、柏崎遺跡群、宇木遺跡群、などと変遷し、邪馬台国時代の古墳ともいわれ る「久里双水古墳」に繋がっていく。 ■弥生時代初めから中期にかけての、領域内の中心的な場所で国王の居所の侯補となれるような遺跡は、福岡県や佐賀 県など北九州を中心に数多く発見されている。福岡県では前原市三雲遺跡、福岡市吉武高木遺跡、春日市須玖遺跡、飯 塚市立岩遺跡、甘木市平塚川添遺跡、そして、佐賀県唐津市では、宇木汲田遺跡や桜馬場遺跡、柏崎遺跡などがその代 表例である。「使者や通訳が往来」しているという記録からみて、中国とこれらの国々の情勢は、お互いに刻々と把握 されていたとみてよい。佐賀県神埼郡神埼町と三田川町にまたがる「吉野ケ里遺跡」も忘れてはなるまい。時代が卑弥 呼の時代とは異なるとはされるが、あれだけの領域をもった国である。当然魏にも知られていたと見て良く、ひょっと したら邪馬台国である可能性も完全にはぬぐいきれないと思う。 ■伊都国の記述はそれまでと異なる点がいくつかある。まず、「東南」と方位があり、「陸行」している。末廬国には なかった官名があり、それは、対馬国・一大国とは異なる。またなんと読むのかもはっきりしない。「代々王がいる。」 「女王に従属している。」「帯方郡の使者が常駐している。」これらは、これまでの大雑把な記述からすればかなり詳 細な情報といえる。 末廬から糸島地方は東にあたり、「陸行する」事を考えると、末盧国から伊都国へは水行では行けないということを意 味しており、伊都国は内陸地にあった国であるという説もある。つまり現在の糸島地方(前原市を中心とする旧糸島郡 ・福岡市西部)は、末廬から東南ではなく、海路によってもいけるではないかと言うのだ。また唐津と前原では長里説 (200km)でも短里説(50km)でも五百里にはほど遠いとする。(唐津-前原間は約27km)。しかし、東 南には「イト」と呼ぶ地方はないし、古名にもない。さらに、見てきたように倭人伝の里数がかなり大雑把であること を考えれば、伊都国は糸島地方としていいのではないかと思う。陸行については、伊都国から更に内陸部へ向かうこと を考えれば、ここらから(末廬)陸上を行ったと解釈しても特に問題はないように思う。旧糸島郡は、前原町のあった 南側地域を怡土郡、北側地域を志摩郡といったが、明治29年合併して糸島郡となり、さらに平成4年(だったかな?) 市制を敷いて前原市となった。この前原市にある、「三雲、井原、平原付近」が伊都国に比定されている。この地域に は標高416mの高祖山があり、456年から768年、大和朝廷の命によって吉備真備が対新羅戦争のために怡土城 を築いたことで知られている。 ■「官は爾支。副は泄謨觚.柄渠觚。」というこの官名については不詳な部分が多い。「爾支」は「ニキ、ジキ、ニギ」な どと呼ばれ、「泄謨觚」は「シマコ、セマコ、セモコ、イモコ」など、「柄渠觚」は「ヒココ、ヘクコ、ヒホコ」などと、注釈 されるが、その他にも色々に読め、後の日本語に対応しているようなものは見あたらない。「彦」や「妹子」などの「子」と も関連するような気もするが、実態は不明である。
■しかしながらその他の多くの官名は、日本の「古事記」「日本書紀」の神代の巻に現れる神名などと一致するものが 多いのは注目される。不彌國の官「多模」は、「万葉仮名の読み方」で正確に「たま」と読め、古事記には「玉の祖の 命(たまのおやのみこと)」「布刀玉の命(ふとだまのみこと)」「宇迦の御魂の神(うかのみたまのかみ)」など列 挙に暇がないほど現れるし、投馬國の官「彌彌」はこれも上古音で「みみ」と呼ぶことができ、「天の忍穂耳の命(あ めのおしほみみのみこと)」「多芸志美美の命(たげしみみのみこと)」「建沼河耳の命(たけぬなかはみみのみこと)」 「神沼河耳の命(かむぬなかはみみのみこと)」など、「みみ」を含む神名・人名はかなり出現する。「卑狗」を「ひ こ」と呼ぶことは定説で、これ又記紀には相当出現するし、「卑奴母離」を「ひなもり」と呼んで後世の「夷守」にあ てる事にも異論はない。安本美典氏は、「爾支」を「ニギ」と呼んで「邇邇芸の尊(ににぎのみこと)」「邇芸速日の命 (にぎはやひのみこと)」の邇芸にあたるとしている。また氏も「泄謨觚.柄渠觚」、及び、奴国の官名「兄(当て字) 馬觚」の呼び方は相当難しいとしながらも、「泄謨觚・兄馬觚」を「しまこ」、「柄渠觚」を「ひここ」或いは「ほこ こ」の可能性が高いとしている。(「倭人語の解読:平成15年6月1日・勉誠出版発行」) ■伊都国の戸数「千余戸」は、この国の重要度からみて少なすぎるのではないかという説がある。「戸万余」の間違い ではないかと言うのだが、魏の使者が常駐したり、代々王がいたり、という国の規模からすれば確かに少ないかも知れ ない。しかし王が居ればこそ、ここに住める一般人は限られていたと想像する事もできる。「王」の存在が明らかなのは、 この伊都国と邪馬台国と狗奴国の三国だけである。「世々王有るも、皆女王国に統属す。」とあるように、伊都国は古 くから卑弥呼を支えていた主要国と見ていいだろう。だからこそ「郡使が往来するとき常に駐まる所。」という邪馬台 国連合国家の中で、外交的に重要な役割と地位を占めていたと考えられる。 ■倭人伝には、伊都国以前は方角、距離、国名と順に記されているのに対し、伊都国以降は方角、国名、距離の順に記 載されており、距離と国名の順序が入れ替わっている。このことを指摘したのは榎一雄氏であるが、その提唱の要旨は、 「倭人伝は、伊都国まで連続に末盧国、伊都国、奴国と読み進む形式で記されているが、伊都国以降は、奴国、不弥国、 投馬国、邪馬台国と、伊都国を起点として読み進められるべきだ。」というものである。これは「放射説」と呼ばれ、 あたらしい倭人伝の解釈として脚光を浴びた。邪馬台国に次ぐ重要な地位を占めている(と思われる)伊都国から、魏 使は様々な国を訪問したという考えに基づく。これは一考を要していい説であろう。 ■【魏略曰】 「又渡海千餘里、至末廬國、人善捕魚、能浮沒水取之。東南五百里、到伊都國。戸万餘。置官曰爾支、副曰曳渓觚・柄 渠觚。皆統屬女王也。」 -------------------------------------------------------------------------------- 東南至奴國百里。官曰ji[冠凹脚儿]馬觚、副曰卑奴母離。有二萬餘戸。東行至不彌國百里。官曰多模、副曰卑奴母離。 有千餘家。南至投馬國水行二十日、官曰彌彌、副曰彌彌那利、可五萬餘戸。南至邪馬壹國、女王之所都、水行十日、陸 行一月。官有伊支馬、次曰彌馬升、次曰彌馬獲支、次曰奴佳[革是]、可七萬餘戸。 東南して奴国に至る。官は兒馬觚といい、副は卑奴母離という。2万余戸あり。東行不弥国に至る。百里。官を多模と いい、副を卑奴母離という。千余の家あり。南、投馬国に至る。水行二十日。官を彌彌といい、副を彌彌那利という。 五万余戸ばかりあり。南、邪馬台国に至る。女王の郡する所なり。水行十日、陸行一月。官に伊支馬あり。次を彌馬升 といい、次は彌馬獲支といい、次は奴佳韃という。7万余戸ばかりあり。 そこから東南の方角へ行くと奴国(今の博多)に至る。距離は百里である。長官をジ馬觚といい、副官を卑奴毋離とい う。二万余戸がある。東の方角へ行くと、不弥国に至る。百里である。長官を多模といい、副官を卑奴毋離という。 千余戸がある。南へ行くと、投馬国に至る。水行(一海を渡ると区別している事から、この表現は川を行くものだ、と の説がある。)で二十日かかる。長官を弥弥といい、副官を弥弥那利という。五万余戸ばかりの人口である。南へ行く と、邪馬台国に到達する。女王の都がある所である、水行十日(と/又はの二説あり。)陸行一月である。長官を伊支 馬といい、次官を弥馬升とい い、次官を弥馬獲支といい、次官を奴佳タイという。七万余戸ばかりの人口である。 ■福岡県春日市。福岡市の東南に位置し、春日丘陵と呼ばれる福岡平野の南部丘陵を形成している。この地方は古くか ら古代の墳墓・遺跡が発見されており、中でも青銅器生産関連の遺物が多いことで注目されていた。記録の最初は江戸 時代にさかのぼる。福岡藩(黒田藩)の国学者であった青柳種信(1766~1835:明和3年~天保6年)が編纂した「筑前 国続風土記拾遺」に、広形銅矛の鋳型の記事が見える。「筑前国那珂須玖村熊野神社神殿所納銅鉾型」というのがそれ で、これは現在も熊野神社が所蔵しているが、種信が書き記した時点で既に熊野神社が保有していたことを考えると、 既にその前に掘り出されていたはずである。又、熊野神社には「王墓の上石」と呼ばれる平板の石板も残されていたが、 これは、明治時代に家を建てるのにじゃまだというので動かしたところ、下に墳墓があり、中から鏡(前漢鏡?)が30 面以上、銅剣・銅鉾・銅戈などの青銅器が8本以上、ガラスの壁(へき)やガラスの勾玉などが多数出土したと言う。 これらの副葬品は既に散逸してしまっているが、上石だけは転々と場所を代え、熊野神社に残っていたもの。 現在は「奴国の丘歴史公園」内に移転されている。 ■「須玖岡本遺跡群」と呼ばれる、春日丘陵に点在する古代遺跡があるあたりは福岡市のベッドタウンであり、古くか ら住居がひしめいている。その為これらの住居の下にも相当の遺跡が眠っていることが想像できるが、現時点ではどう しようもない。春日市教育委員会では、どんな小さな場所でもいいから立て替えるときには必ず調査を行わせてほしい と市民に呼びかけ、市民もこれに答えている。勿論調査後遺跡は再び埋め戻され、本来の住宅が建設される。かっての 王墓の跡も今は埋め戻され、わずかに案内板が立てられているだけで、上には現代人が住んでいる。 ■「岡本遺跡」では今から2000年前(弥生時代中期)の甕棺墓・木棺墓・土壙墓・祭祀遺構・住居跡が見つかっている。 又遺跡公園内には、奴国王の墓の上を覆っていたという大石を熊野神社から移設しているが、この墓については、同じ く公園内に創設された「歴史資料館」に解説がある。資料館にはこの他、須玖岡本遺跡群から発掘された遺物が多数展 示されている。この遺跡がほんとに「奴国」の中心地であったかどうか、又「王墓」とされている遺構もほんとに王の ものかどうかについては異論もある。しかし現在までの所、奴国に相当すると思われる地域(福岡市から春日市、大野 城市、筑紫野市あたり)からは、この遺跡群を上回る規模の遺跡は発見されていないのだ。従って今の所、「奴国の都」 の最有力候補地と言ったほうが正確かもしれない。 ■全国で初めてガラス製品の製作工房跡がわかったのも、この春日丘陵の須玖五反田遺跡である。ガラスの勾玉の鋳型 が出土した遺跡は、これまでに9つが知られている。大阪府茨木市・東奈良遺跡、山口県菊川町・下七見遺跡の2ケ所 の他は、全てこの春日丘陵とその周辺である。ガラス製品の製作は弥生中期に始まると考えられているが、中期の鋳型 が出土する所では具体的な製作を示す他の遺物や遺構がわかっていない。須玖五反田遺跡では、勾玉鋳型が複数個、坩 堝(るつぼ)、勾玉の未製品などが出土して製作を裏付けているが、時期は後期後半と見られている。 須玖五反田遺跡を発掘調査した春日市教育委員会の吉田佳広氏は、「溶解温度の低いガラスは青銅に比べて遙かに鋳造 し易いが、その製作に関して専門知識と熟練が必要な事は青銅器と変わりなく、原料の入手や製造技術にも共通する点 が多い。青銅器の工人の中でガラスを扱う技術を習得した者は、青銅器工房の一角において、さまざまな青銅器ととも にガラス製品の製作を行っていたものと思われる。」と述べ、ガラス製品の製作が推測される遺跡では、同時に青銅器 生産に関する遺物も伴っている事を指摘している。 ■さてついに邪馬台国へ到着するが、周知のようにその位置は未だ判明していない。不弥國から南へ水行で二十日かか ると投馬國へ到着し、さらに南へ水行十日、陸行一月で「邪馬台国」と言うことになる。奴國が博多湾岸から春日市の あたりだと想定すると、東の不弥國は、従来通り宇美町・飯塚市・嘉穂郡あたりになり、その南は三井郡から甘木・朝 倉地方、或いは浮羽郡・久留米市を含むエリアが考えられるが、水行の意味が不明だし、川を降っても(どの河かがま た問題になるが、宝満川あたりか。)1日で下ってしまう。20日もかからない。有明海へ出て、更に筑後川を遡り甘 木・朝倉へ行くことはできるが、これとて4,5日もかからないだろう。さらに、その投馬國から水行十日、陸行一月 と言うことになるともうお手上げである。大阪風に言うと「頭湧くねぇ」という事になる。日数日程を度外視して、不 弥国から南へ南へと下ってくれば以下の図のようになるのだが、ここまで日数・行程を無視するには当然それなりの論 理が必要になる。
■上の図は、倭人伝の「倭国」描写が九州島に限られているという前提に立てば、非常にスッキリした位置に納まって いるようにも思えるが、日程を無視しているし、陸行や水行などの手段も全く考慮していない。 -------------------------------------------------------------------------------- 自女王國以北、其戸數道里可得略載、其餘旁國遠絶、不可得詳。次有斯馬國、次有已百支國、次有伊邪國、次有都支國、 次有彌奴國、次有好古都國、次有不呼國、次有姐奴國、次有對蘇國、次有蘇奴國、次有呼邑國、次有華奴蘇奴國、次有 鬼國、次有爲吾國、次有鬼奴國、次有邪馬國、次有躬臣國、次有巴利國、次有支惟國、次有烏奴國、次有奴國、此女王 境界所盡。其南有狗奴國、男子爲王、其官有狗古智卑狗、不屬女王。自郡至女王國萬二千餘里。 女王国より以北はその戸数・道里は得て略載すべきも、その余の旁国は遠絶にして詳らかにすることを得べからず。次 に斯馬国あり。次に己百支国あり。次に伊邪国あり。次に郡支国あり。次に彌奴国あり。次に好古都国あり。次に不呼 国あり。次に姐奴国あり。次に対蘇国あり。次に蘇奴国あり。次に呼邑国あり。次に華奴蘇奴国あり。次に鬼国あり。 次に為吾国あり。次に鬼奴国あり。次に邪馬国あり。次に躬臣国あり。次に巴利国あり。次に支惟国あり。次に烏奴国 あり。次に奴国あり。これ女王に境界の尽くる所なり。その南に狗奴国あり。男子を王となす。その官に狗古智卑狗あ り。女王に属せず。郡より女王国に至ること万二千余里。 女王国より北の方角についてはその戸数・道里は記載できるが、その他の周辺の國は遠くて交渉が無く、詳細は不明で ある。次に斯馬国があり、次に已百支国あり、次に伊邪国あり、次に都支国あり、次に弥奴 国あり、次に好古都国あり、 次に不呼国あり、次に姐奴国あり、次に対蘇国あり、次に蘇奴国あり、次に呼邑国あり、次に華奴蘇奴国あり、次に鬼 国あり、次に為吾国あり、次に鬼奴国あり、次に邪馬国あり、次に躬臣国あり、次に巴利国あり、次に支惟国あり、次 に烏奴国あり、次に奴国あり。これが女王の(権力の)尽きる所である。その南に狗奴国があり(今の熊本か?)、男 子の王がいる。その長官は狗古智卑狗であり、(この國は)女王國に隷属していない。帯方郡より女王国に至るまでは 一万二千余里である。 ■この部分はもっぱら魚拳の「魏略」を参考にして書かれており、三国志は魏略を多く引用していると言われる。 ここにいう「女王国より以北はその戸数・道里は得て略載すべきも、その余の旁国は遠絶にして詳らかにすることを得 べからず。」という部分は注目に値する。これまで述べてきた戸数・道里が略載であると明言している。つまり戸数・ 道里は確実なものではないと陳壽自身認めている事になる。以下の余旁国二十一国についても、学者によってはまるっ きり架空のもので、いちいち検討するのは無駄であるとして、全く言及しない人もいるくらいだ。二十一国を順に書き 出すと「 1.斯馬國 2.已百支國 3.伊邪國 4.都支國 5.彌奴國 6.好古都國 7.不呼國 8.姐奴國 9.對 蘇國 10.蘇奴國 11.呼邑國 12.華奴蘇奴國 13.鬼國 14.爲吾國 15.鬼奴國 16.邪馬國 17.躬 臣國 18.巴利國 19.支惟國 20.烏奴國 21.奴國」 となってまた奴國で終わっている。 ■ここで倭人伝に登場する国々とその行程をまとめてみると以下のようになる。 国 方角 距離 特記 ========= ==== ============= ====================================== 狗邪韓国 東南 七千余里 ・帯方郡の東南 ・海岸をめぐりて水行。 ・韓国を経て、あるいは南あるいは東。 対馬国 ? 千余里 ・始めて一海を渡る。 一大国 南 千余里 ・瀚海を渡る。 末盧国 ? 千余里 ・一海を渡る。 伊都国 東南 陸行五百里 奴国 東南 百里 不彌国 東行 百里 投馬国 南 水行二十日 邪馬台国 南 水行十日陸行一月 ・帯方郡より女王国に至るに万二千余里。 余旁国 ? ? ・遠絶にして詳らかにするを得ず 二十一国。 狗奴国 南 ? 倭種の国 東 千余里 ・海を渡る。・女王国の東。 侏儒國 南 四千余里 ・倭種の国の南 ・女王国から四千余里・人長三四尺。 裸国・黒歯国 東南 船行一年 ・侏儒國の東南。 ■これを解釈して、邪馬台国畿内説、九州説が論戦を重ねているのは周知のごとくであるが、その概略を図示すると概 ね以下のようになる。
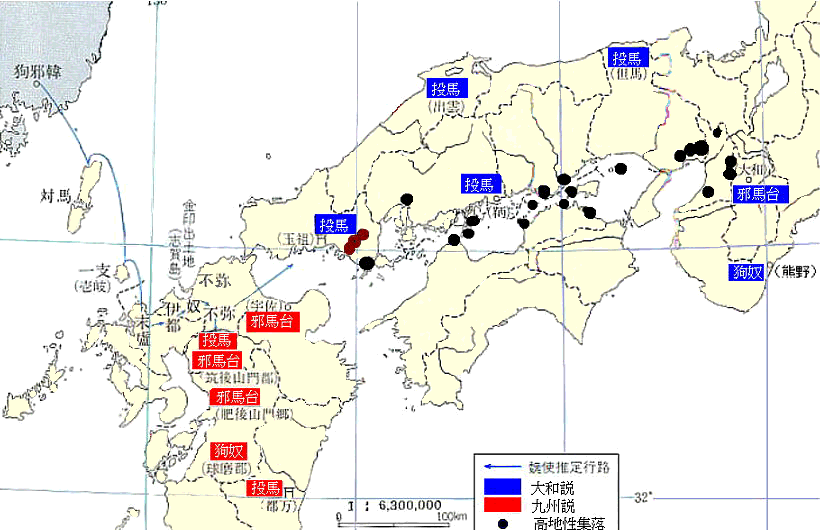
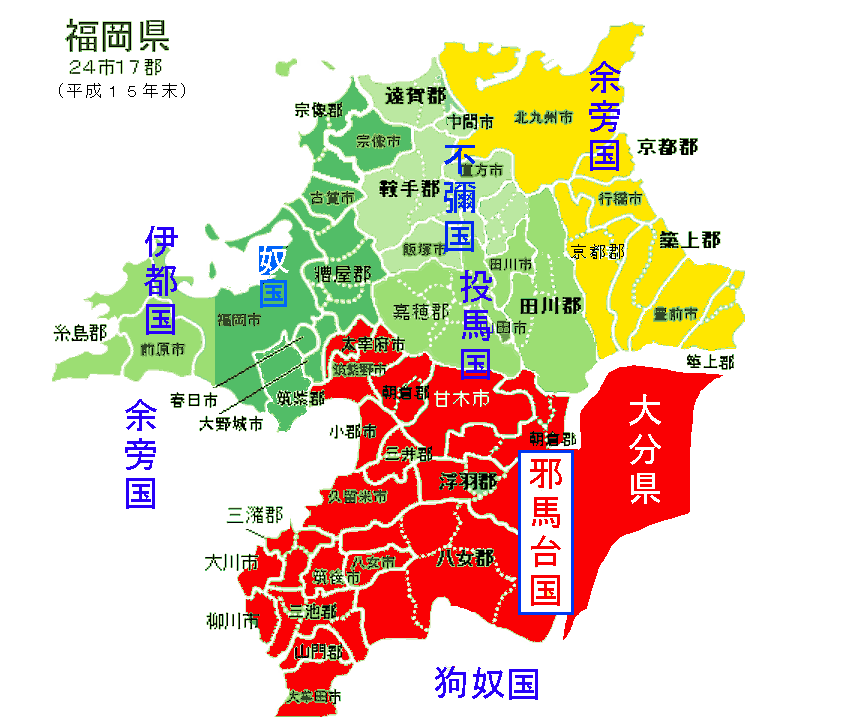
 邪馬台国大研究・ホームページ / わちゃごなどう?/ 本編
邪馬台国大研究・ホームページ / わちゃごなどう?/ 本編