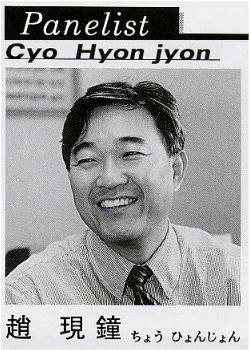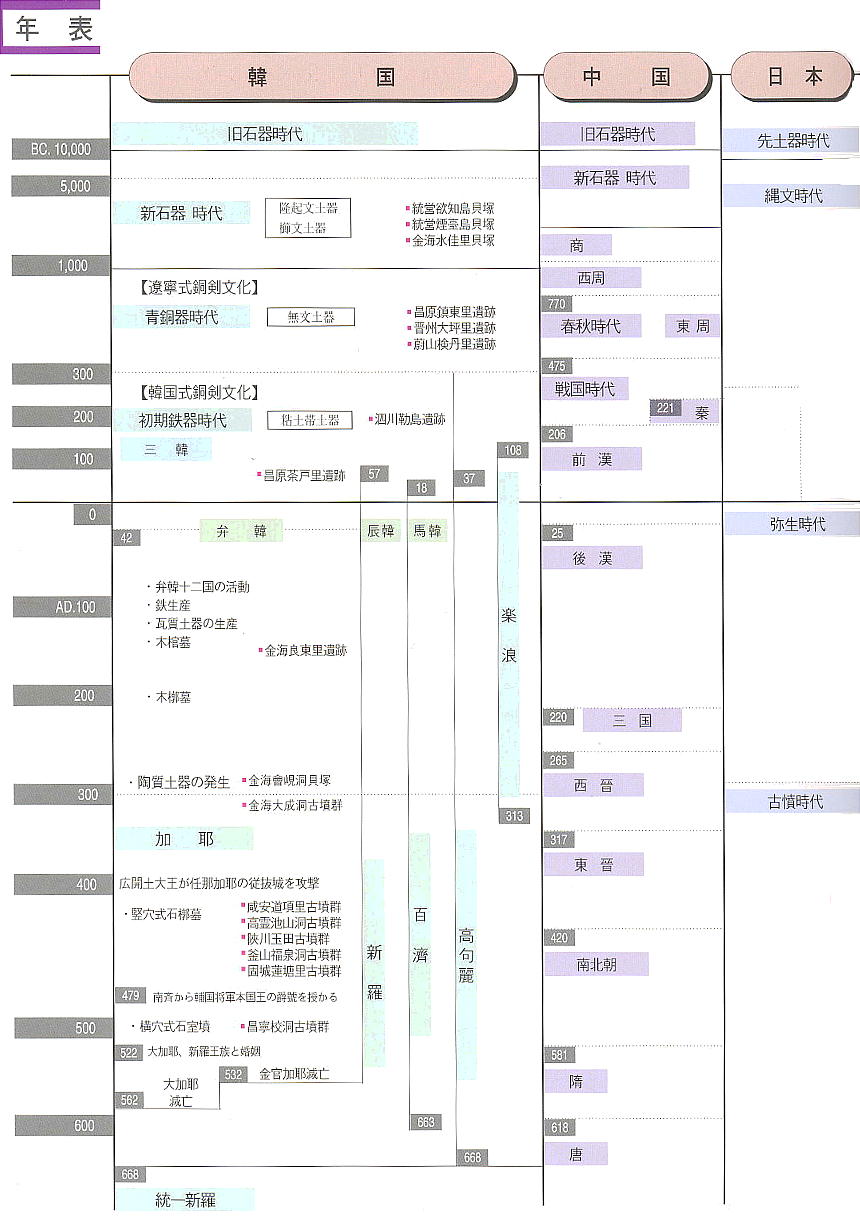Music: PS I love you
Music: PS I love you
3.基調報告 韓国の初期稲作
趙現鐘(Cyo Hyon Jyon)
【講演者プロフィール】
趙現鐘(Cyo Hyon Jyon)
1956年生まれ。金南道潭陽出身
国立済州博物館館長 文学せきし(?) 考古学
全南大学校 文理大学 史学科卒
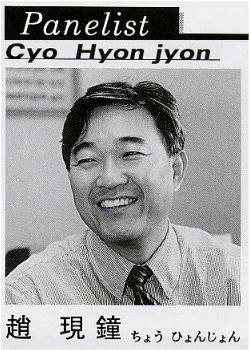

【1.稲作の出現時期】
(1).今まで韓半島で確認された稲作資料のうち、初期資料は約20箇所の遺跡から発見されている。炭化米をはじめ、植物遺存体が
中心であり、その時期はおおよそ新石器時代中期から青銅器時代の前期後半(中期)に至っている。
(2).1990年金浦佳■(山と見)里泥炭層から採取された稲籾は4,010+-25BPと報告されており、問題もあるがもし報告が正しいと
すれば韓国での稲の出現は新石器時代中期段階にまでさかのぼる可能性がある。
(3).今まで新石器時代で最初に出現した初期農耕資料は黄海道智塔里、平壌南京などの遺跡で、出土した稗(ひえ)と粟(あわ)
等畑作による雑穀栽培である。しかし、新石器時代後期になると全般的に農具体系が維持されるなか、大小石斧類が一部増加
する傾向がみられる。これは人口増加によるものと考えられる。新しい農耕方式即ち稲作の受容を意味している。
(4).1995年金海所里貝塚から出土した胎土分析で、我が国(韓国)初の稲のプラントオパールが検出された。約3,500〜3,000年前)
と推定される。この結果は新石器時代後期の遺跡から出土した遺物であることを示す、比較的信頼度が高い資料である。
(5).上記は、安田喜憲による栄山江近辺の佳興里と洛東江周辺の礼安里堆積層での花粉分析結果(約3,000年前)とも一致している
し、中国東北地方の稲資料ともある程度附合している。
(6).以上により、韓半島稲作の出現時期は、最近、土器の珪素体分析からも確認されているように、新石器時代後期と推定できる。
そしてそのまま、新しい技術体系の受容、生活用式の変化を伴い青銅器時代を迎える。
【2.稲作類型】
(1).韓半島の稲作の受容は華北の類型と密接な関係がある。華北地域は伝統的な粟作地帯で畑作が中心である。
この地域の稲資料は仰詔文化段階から発見されているが、陸稲栽培の資料はない。
(2).龍山文化前期に当たる山東省揚家圏の稲籾(2,440+-130B.C)も水稲として鑑定され、遼東半島大連市の大嘴子遺跡から出土し
た炭化米も水稲である可能性が高い。
(3).紀元前1世紀後半頃、汎勝之が書いた山西省乾燥農業地帯の農法でも、さまざまな栽培作物の中、稲は水田のみに言及してい
る。
(4).従って、韓半島で受容された稲作類型は、このような華北類型の水稲作が多い。この点はまだ資料の補充が必要であるが、稲
作初期に陸稲が受容され、焼き畑などから先に栽培された後、水稲栽培方式へ転換されたとは言いにくい。特に、韓半島での
焼き畑稲作は自然条件上からも可能性がない。
【3.畑面の検出と分析】
(1).韓半島で確認された先史時代の畑面は、晋陽大坪の玉房と漁隠地区などの慶南地域一帯から調査されたものである。
畑面で出土した遺物には籾痕土器が相当数あり、石鑿・片刃石斧・半月形石包丁などのいわゆる木工具と収穫具が出土した。
(2).畑土壌の分析結果から、稲のプラントオパールが確認されたが、微量であり、陸稲の根拠としては採用できない。
(3).漁隠1地区4号土杭から炭化米が出土したが、出土した穀物は粟が主体で、畑面では稲資料が確認されなかった。従って、大
坪地域の広大な畑面では、稲が栽培されていなかったことがわかる。いままで陸稲の痕跡は1992年光州新昌洞遺跡で調査され
た紀元前2-1世紀代の畑面が唯一である。
(4).とすると、大坪地区の炭化米の栽培地は何処にあるのだろうか?それは畑面と住居が分布する自然堤防によって保護され、川
辺から離れた背後湿地或いは低台地上に位置した水田で、水稲栽培された可能性が高い。■(さんずいに美)沙里の長方形系
の孔列土器住居趾についても同じようなことが言える。
【4.韓半島の初期水田】
(1).韓国で水稲作開始を示す考古学的資料は、蔚山玉■(山と見)遺跡と諭山麻田里遺跡で調査された青銅器時代の水田である。
海抜25−30m程度の丘陵部に住居と墳墓などが位置し、水田は谷間部の低地帯に造成されている。
(2).蔚山玉■(山と見)遺跡と諭山麻田里遺跡は、耕作面下部で発見されたFe(鉄)およびMn(マンガン)の集積層の確認、
畦の存在、水路施設の完備などから、当初から発達した水田構造をもった給水型の乾田として出発している事が明らかである。
(3).2つの遺跡を開田形態から見ると、3坪を基準とした小区画水田である。水利の問題が大きく作用したと考えられる。
傾斜地という地形的な条件を考慮した灌漑施設になっている。
(4).以上から、韓半島で調査された水田資料は、青銅器時代の前期後半から出現し、水路を通じた取水・排水などの灌漑施設を具
備した形態で、面積はおおよそ3坪程度の小区画で造成されているのが確認できた。
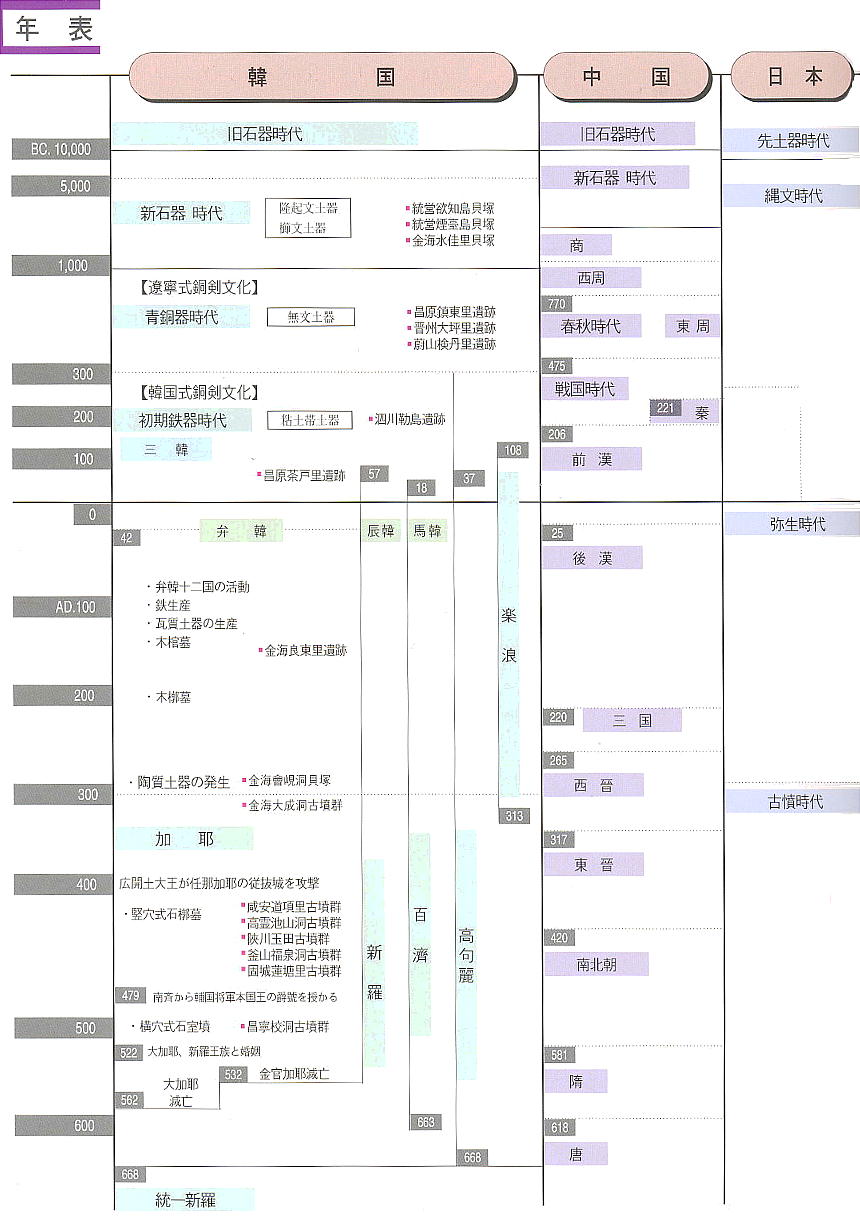
大韓民国国立金海博物館発行「同館案内目録−日本語版−」より転載。

【講演を聴いての私の感想】
◆大変失礼ながら、全く面白くなかった。レジメを読むだけに終始した講演会など日本でもかってお目に掛かった事がないだけに、
一体どうした事かと思ってしまった。読んでいくのを聞いてても、間に通訳が入るものだからたどたどしく、全く興ざめだった。
◆講演会の1週間ほど前に韓国へ行って来たばかりだったので非常に期待していた。金海(キメ)貝塚にも行ったし、礼安里遺跡も
見た。韓国に対して妙に親近感を感じて戻ったばかりだったので、どんな話が聞けるのだろうとわくわくしていたが肩すかしもい
いとこだった。韓国の講演会というのはこんなものなのかなとも思ったが、いつぞや奈良で聞いた、年輪年代法をやっている韓国
の研究者はもっとおもしろい話を聴かせてくれたので、多分この趙さんのやり方なのかもしれない。
◆それとも、趙さんは日本に対してあまりいい印象を持ってないのか、それとも教科書問題あたりで日本に対して頭に来ていて、こ
んなおざなりな講演をしたのかな、と妙に勘ぐってしまった。
◆或いは、趙さんはまだこんな講演会には慣れていないのかもしれない。国立済州博物館は最近出来たばかりで、趙さんは初代館長
だそうだから、忙しくて準備ができなかった可能性もある。いずれにしても、次回はもっと面白い講演をお願いします。



邪馬台国大研究ホームページ / 学ぶ邪馬台国 /chikuzen@inoues.net
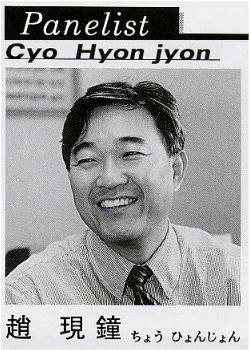

 Music: PS I love you
Music: PS I love you