
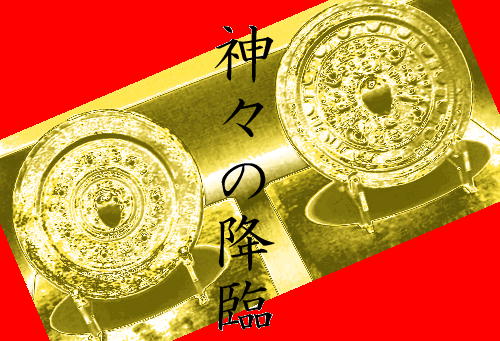
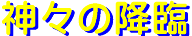
弥生時代を迎えるまでの日本人の心の中にあった「神」という概念は一体どのようなものであったのだろう。神道の元にな ったと言われる「自然崇拝」(アニミズム)は、勿論その第一義に挙げられる。大自然や暗闇や、人知を越えた自然現象に 対して恐れおののき、やがてそれらを「神」として奉(たてま)った縄文人達の心象世界は、今でも世界の未開民族の間に しばしば見られるところである。古来より我が国では、「神」は至るところに在り(汎神論)、山や川、木や草、風や雨、 自然現象のあらゆるものが「神の技(わざ)」とみなされ、やがて山岳は「神々」のおわす聖域ともなっていく。(今でも 例えば奈良の三輪神社は三輪山そのものがご神体である。)この考えは現代にも形を変えて生き残っている。修験道などは その典型であろう。これは縄文或いはその前代からの、我が国における原初宗教のなごりなのだ。 我々は今、神社の中へ入る前に手を洗い口をすすぐ。これは「禊ぎ」(みそぎ)である。「魏」の使者が「倭」に来て葬式 を見ているが、その書き残した所によれば、「埋葬が終われば家の者は川へ行って禊ぎをする。」とある。我が国では古来 から、「けがれを清める」ことについてはえらく熱心であり、今でも葬式から帰ったら家の中に入る前に塩をかけられる。 精進料理は「魏志倭人伝」の頃からある。喪に服している者は肉を食べないとある。つまり、汚れや穢れを身につけた者は 本来の姿ではないのである。「死」を見取った者は汚れており、「肉食」は穢れなのだ。2000年前に、既にこういう概念が 存在している。言い換えれば、我々の心の中にこういう概念は2000年以上住み着いているのである。 一方で、「自然崇拝」以外にも「神」の概念は成立していったものと思われる。縄文時代の末期頃には権力者を「神」と崇 (あが)める制度・慣習・概念が既に成立していたのではないだろうか。 弥生時代に入ってからの渡来人およびその子孫 達を「天津神(あまつかみ)」として奉り、渡来人以外の、縄文から続く権力者達を「国津神(くにつかみ)」と崇めたの ではないだろうか。我が国の文献に残る数々の神話は、この頃の様子を書き残したもののように私には思える。九州から瀬 戸内海を通って大和平野へ入った豪族が、おそらく3世紀から4世紀にかけて、各地の先住豪族達をつぎつぎに服従させて いく過程の中で、自分たちが奉じる神々を天津神、先住民の神々を国津神と区別していったのだろう。

「記紀」によれば、高天原に居た神々達は、出雲に「国譲り」を迫り、これを果たして天照大神の孫にあたる「天津日高日 子番能邇邇芸命(あまつひこひこほのににぎのみこと):以下、ににぎのみこと」をその長官として出雲に送り込む。勿論 神話は、天地創造や日本列島の成立や、伊邪那岐(いざなぎ)、伊邪那美(いざなみ)による神々の生成なども記述してい るのであるが、この「出雲の国譲り」などは明らかに神々による現世支配であり、背景に歴史的な史実が存在していた事を 窺わせるに十分な写実的とも思える内容を持っている。 天照大神は、ににぎのみことを筑紫の日向の高千穂峰(たかちほのみね:その場所を巡っては宮崎県高千穂峡と鹿児島県 (一部宮崎県にかかる)霧島連峰の高千穂峰との二説があるが、それ以外を唱える説もある。)に遣わし、葦原中国(あし はらのなかつくに:高天原から見た下界、日本列島の事)を治めるよう下命する。これが神話に謂う「天孫降臨」であり、 神々が雲上の高天原から現世に降りて来た初源とされる。 考古学的、歴史学的な見地から考察すると、この「天孫降臨」こそは、縄文時代から弥生時代へ移り変わろうとする我が国 の様子を書き表したもののように思える。「天孫降臨」以降の神話は、考古学的な所見と比較すると明らかに、それに続く 弥生時代、古墳時代の事を書き残したものであると言っていい。「天孫降臨」を外来民族による我が国への渡来、そしてそ の渡来人達の大和への東遷と考えると考古学的知見、歴史学的考察から見て古代考証が驚くほど説明可能のことに気づく。 神話の舞台はその殆どが九州であり、しかも北九州に集中している。ついで多いのが出雲であり、大和地方はごくわずかで ある。これは北九州に「天津神」がいて出雲の「国津神」から領土を奪い、そして大和地方を平定すると考えればしっくり くる。






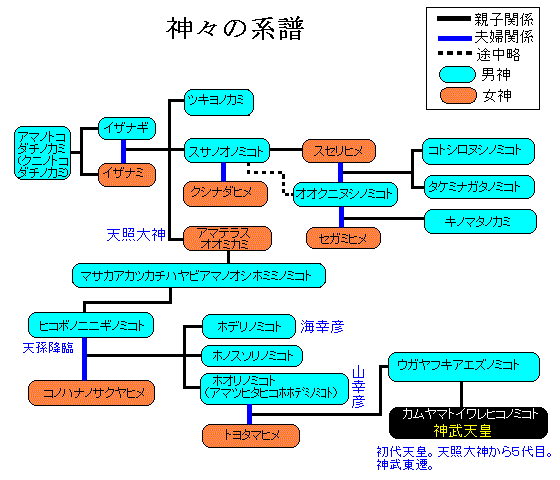
天地の始め、高天原にアマノミナカヌシ・タカミムスビ・カミムスビの三神が現れ、続いて、国土がまだ水に浮く油の ようでクラゲのように漂っている時に、ウマシアシカビヒコジ・アマノトコタチの二神が現れる。この五神は「特別/ 別格」という意味合いで「別天津神」(ことあまつかみ)と言う。次に「神世七代」(かみよななよ)と言って独神 (ひとりがみ)が二代、その後男女二神の対偶神が五代続く。その最後にイザナギ(伊邪那岐)、イザナミ(伊邪那美) が現れる。 これは「古事記」の神話部分冒頭の記述で、「日本書紀」における神々の系譜は若干違った構成をとり、また神の名も かなり異なっている。「書紀」では最初の神はクニノトコタテノミコトである。しかし二書ともにイザナギ・イザナミ 以前は、タカミムスビ(高御産巣日:高木の神)以外はただ名前の羅列であって特記する記事もない事から、神話が完 成していく過程で適当に加筆されたものと考えられる。 この後神話は以下のように続いていく。 イザナギ・イザナミによる日本列島の生成や神々の創造。 イザナギが黄泉の国から逃げ帰って禊ぎを行った際、右目からツクヨミ、左目からアマテラス、そして鼻からスサノオ が出現する。 スサノオの狼藉やアマテラスの岩戸籠もり。 スサノオは高天原を追われ出雲へ流される。スサノオはここで八俣大蛇(ヤマタノオロチ)を退治してクシナダヒメと 結婚する。 「古事記」ではこの六代後にオオクニヌシ(大国主)が出現するが、「日本書紀」ではオオクニヌシはスサノオとクシ ナダヒメの直接の子供という事になっている。オオクニヌシは幾つか別名を持ち、「因幡の白ウサギ」など多くの逸話 が残っているが、これは本来別々の話であったものがオオクニヌシの話として集大成されたものとの見解が有力である。 オオナムチという名は「日本書紀」におけるオオクニヌシの呼び名である。アマテラスは、出雲の国は自分の子が支配 すべきであると考え、タカミムスビと図って出雲に 圧力をかける。オオクニヌシは出雲の国を高天原に譲り、豪壮な宮殿で隠居する(のちの出雲大社という説が有力)。 この国譲りの後、ヒコボノニニギが高千穂の峯に降ることになる。(天孫降臨)ヒコボノニニギから三代に渡って日向 に住んだ神々を日向三代と呼ぶ。そしてカムヤマトイワレヒコが東を目指して遷都の旅に出る。これを「神武東遷」と 言い、イワレヒコは神武天皇と呼ばれ奈良の橿原に都を定め、天皇家の始祖となる。 これが「記紀」にいう所謂日本神話である。

戦後の歴史学は、神話性を排除するため教科書から「古事記」や「日本書紀」の神話内容を一切排除してしまった。言及し たとしても、文字通り「神話」であると断定しその内容に全く歴史性を認めなかった。この立場は、今日でも「津田史学」 として有名であるが、東京大学の白鳥庫吉の弟子であった津田左右吉による処が大きい。津田は、『古事記及び日本書紀の 研究』を始めとした一連の著作において「記紀」の歴史性を否定し、これらは大和朝廷が後世自己の正当化のために作り上 げたものであるとした。津田自身は天皇制否定論ではなくむしろ天皇家には「尊敬の念を抱いている。」という人間であっ たようだが、学問的には述べたような立場に立っていた。 戦前・戦中の「天皇支配」による反動は、戦後になって人々の心の中に「反天皇制」感情を深く植え付けるという形になっ て現れ、解放された戦後の自由な空気のなかで、歴史学という学問分野における開放感も又一般人の気持ちと同じであった。 一部の歴史学者、又考古学者の多くは、特に若い者はこの「津田説」を素直に受け入れたようである。「神話」を研究する のは文学や民俗学の対象としてであって、歴史学に置ける「神話研究」などは科学的ではないとされたのである。長い間 「津田史」は歴史・考古学会の主流であった。 しかしながら、20年ほど前から始まる一大発掘ブームと、最近のラッシュとも言える発掘調査による成果は、これまで「お 話」とされてきた文献上の記述が史実であった事を続々と証明し出した。「城柵」「楼閣」は存在したし、出雲には古代多 くの先進文化が実在していた。糸魚川のヒスイは遠く朝鮮半島からも出土したし、我が国独自と考えられていた前方後円墳 が、韓国の墳墓にも用いられていた。 記録は事実を語っている。この事にようやく学界も気がつきだしたのである。同志 社大学名誉教授になった森浩一氏もまだ助教授時代にこう言っている。「今まで省みなかった神話にでてくる色んなことが 不思議と考古学的な資料と合致するんですね。こりゃ「記紀」をもう一回読み直さなくちゃいかんぞ、と思いましたね。」 近年ある著名な歴史学者は、「最近の歴史考察における論評を見ていると神武東遷だとか天照大神だとか、まるで戦前の皇 国史観のような論評が目立つ。これは歴史学を逆行するような風潮で、強く戒めねばならぬ。」と述べているが、これは 「学問」と「政治」の区別がついていない。「神話」を重視しようという歴史学における風潮は、再び天皇を国家元首にい ただいて帝国主義を復活させようなどという意図はさらさらないし、むしろそういうモノとは対局にある。「神々」とそれ を成立させてきた我々日本人の思想体系と思考体系を明らかにする事によって、二度と再び不幸な歴史は繰り返すまいとす るものである。また、世界中の国々で、その国独自の神話は重要な意味を持つ。 古代の人々がいかにしてその神話を成立させたのか、またいかにしてその物語を伝承し続けたのかを考えるとき、そこにそ の民族の成立要因が潜んでいる事が多いのである。 その国の歴史を語るとき、文献の力をかりずに構築できるような歴史はない。無ければ別だが存在するのなら、古い言い伝 えや出来事を記録したものは何らかの歴史的な事実を語っている、と見たほうがよい。遺跡・遺物はそれだけでは唯の古物 である。文献の光があたってはじめて輝くのである。「記紀」が真に天皇家の成立を肯定するために創作された物語である ならば、どうしてああまで近親和合や「糞尿」「女陰/まぐわい」と言った言葉で物語を埋め尽くすのであろうか。権威を 貶めこそすれ、決して天皇家を賛美したものにはなっていない。



私は「天照大神」=「卑弥呼」とする説に賛成である。 今までの邪馬台国論説の中ではこの説が一番、「邪馬台国」を含む縄文・弥生・古墳時代の我が国古代を説明するのに合理 的だと考えるからだ。だとすれば、高天原も雲上ではなくこの地(日本列島)にあって、弥生時代の事と言うことになる。 出雲は高天原とは独立して権勢を誇っており、それもおそらくは北九州を経由せずに中国或いは朝鮮から直接出雲を中心と した山陰地方に根付いた文化圏だったと考えられる。(「出雲王国は存在したか」参照) では高天原はどこにあったのか? 当然大和(奈良)ではありえない。ここは出雲の属国であった可能性が高いが、やがて 日向からやってきた「神武天皇」に滅ぼされるからである。当然「高天原」は大和以外でなければならない。 当時それだけの勢力と新進性を持った地方は九州、それも「北九州」しかあり得ない。勿論、北九州自体もその昔(縄文時 代から弥生にかけても)、渡来してきた人々によってその先進性はもたらされたものであるが、神武東遷の頃には既に、 「高天原」=「邪馬台国」時代を経て、古代国家の萌芽が確立され始めていたと考えられる。 この勢力に迫られ「大国主の尊」(おおくにぬしのみこと)は「出雲」を「高天原」に譲り渡す。そしてその勢力は近畿地 方にも進出し、大和盆地に、やがて律令国家の礎になる「大和王朝」の種子を蒔く。北九州からの勢力は日本海あるいは瀬 戸内海を船で攻め入ったと思われる。この故事が天の磐舟という事になるのだろう。 神武天皇が日向から大和へむかう途中においても、多くの神々に遭遇するが、これらは地元に昔から勢力を持っていた豪族 即ち「国津神」と考えて良い。まず豊予海峡で出迎えて水先案内に立つ漁師が、「吾が国津神、名は珍彦(うずひこ)」と 名乗る後の「椎根津彦」(しいねひこ)で、大和国造の祖神である。次に、宇佐の地で一行を歓待するのが、「宇沙津比古 ・比売」(うさつひこ・ひめ)という宇佐国造の祖神。東征軍を難波で頑強にさえぎった「長髄彦」(ながすねひこ)や、 高天原から建御雷神が天降した霊剣を献上して協力した熊野の高倉下(たかくらじ)、兄が抵抗し弟が服従した宇陀県の土 豪、さらには吉野でも「吾が国津神」と名乗った贄持之子(にえもつのこ)と井氷鹿(いひか)と石押分之子(いわおしわ くのこ)など、それぞれ協力者であったり敵対者であったりするが、いずれもその土地土地に根を張った土豪・豪族の首長 や祖神と考えられる「国津神」である。さらには、かくして大和を平定した神武天皇が后に選んだのも三輪山を支配する国 津神「大物主神」の娘である。 この故事は象徴的ではないか。渡来人或いはその子孫達は、縄文の古来から日本に勢力を持っていた神々とこうやって平和 的に融合・同化していったのであろう。同様の展開が、おそらく日本中において進行していったのではないかと思われる。 これに続く古墳時代は、おそらく「高天原」が故国から招聘した、第二・第三・第四次(或いは更に)の渡来人達が日本列 島に馬を持ち込み、文字通り列島を駆けめぐった時代となる。ヤマトタケルの熊襲征伐、東国遠征などはまさしく古墳時代 の戦いの様相を呈している。 ヤマトタケルは東国遠征の帰りに伊吹山の神々と戦って深手を負うが、それは「草薙の剣」を忘れてきた(置いてきた)た めであり、この傷が元で命を落とす。ここに登場する「息吹の神々」はあきらかに「国津神」であり、渡来以前から日本に いた権力者達と考えて良い。 これら一連のストーリーが、「記紀」神話における我が国の神々達の活動として記録され現存しているものと考える。つま り、縄文時代から日本にも「神」は存在し、それは自然や超現象を崇拝する精神的な思想部分と、当時権勢を持っていた豪 族の集団とに冠された。そして、人の集団である「神々」はやがて渡来系の「神」たちと融合したり、戦って或いは負け或 いは勝ったりしながら歴史の中に埋没していったものと考えられる。大和朝廷成立後は「天皇」「仏教」がこの国における 新たな「神」の位置につくが、古代からの日本独自の「神々」もまた日本人の心の中にしっかりと位置し続けることになる。 そして1000年以上の時を経て、今我々は、心からも生活からも、あらゆる「神々」を遠ざけているように思えるが、それに ついては別の機会にふれる事にしよう。
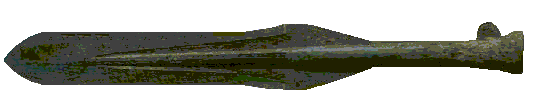

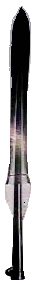
神話の第一ステップとも言える、伊邪那岐・伊邪那美の日本列島形成に用いられる道具は矛(ほこ)である。2人は海の中で矛をかき回し矛先からこぼれ落ちるしたたりで、「おのごろ島」という島を造る。ここに降って、SEX(と思われる表現)で次々と日本の国土を造って行くのである。「古事記」には、天の神々が2人に「天(あま)の沼矛(ぬぼこ)を授けて」とあるが、矛が祭祀用に用いられるのは明らかに「弥生時代」である。又、今日その出土地域は、北九州をはじめとする西日本に集中している。
素戔嗚尊(すさのおのみこと)が出雲で「八俣の大蛇」(やまたのおろち)を退治したときに尾の中からでてきたという剣は、一般に「三種の神器」の一つとして知られるが、今日これは天皇家の「神宝」とされ、名古屋の「熱田神宮」にある(と言われている)。誰も見た者はいないが、古来よりこの剣は弥生時代の有柄銅剣(吉野ヶ里からも出土した)であろうとされている。同じく「古事記」をはじめから読み進んでいくと「天の岩戸」物語までの間だけでも、今日我々が博物館で見ることのできる「弥生時代」の遺物を表現した描写が繰り返し登場する。即ち、「長い剣」、「剣の柄」、「御剣」、「左の手に着けた腕輪」、「右の手に着けた腕輪」、「大きな勾玉」、「靭(ゆぎ)」、「矢」、「玉の音」、「玉の緒」、「珠」、「鏡」、「大きな鏡」等々。
「邇邇芸の尊」(ににぎのみこと)が降臨に際して高天原から持ってきたという「八咫の鏡」も「三種の神器」の一つで、現在伊勢神宮にあるという事になっているが、福岡県前原市の三雲遺跡から出土した「内行花文鏡」を想定する学者も多い。同じく「八尺の勾玉」(やさかのまがたま)も現在皇居にある(と言う事になっているが、今日では、天皇自身もこの「三種の神器」は実見できない。したがって実物を見た者は誰もいないのである)。三種の神器は「剣」「鏡」「玉」である。これらは九州の特に北九州の弥生墳墓および畿内の古墳から出土する。
これらの事実からみて、神話の時代を「縄文時代」と言う人はいないだろうし、「白鳳時代」とも言えないと思う。明らかに「弥生時代」「古墳時代」の遺物について語っているし、状況的には「古墳時代」よりも「弥生時代」の方に分がありそうである。
だとすれば、「神々」は誰で、どこから降臨したのか、おのずと結論は出ているように思う。

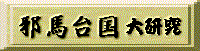
邪馬台国大研究・ホームページ / 古代史の謎 / 神々の降臨
このHPの画像の幾つかは、http://home4.highway.ne.jp/koiduka/the%20second.htmの「時のふし穴」さんから拝借しました。付記して謝意を表します。