 Music: Fool hill
Music: Fool hill

三十年以上前の学生の頃、天皇制について友人達と議論したことがあった。天皇制廃止論や擁護論、維持論などさまざま な意見が飛び交う中、法学部の奴が言った言葉を今でも鮮明に思い出す事がある。「天皇は人間じゃないんよ。」勿論動 物としてという意味ではない。「神」だからというのでもない。法的には、という意味である。現在天皇・皇族を含む皇 室の制度は、昭和22年に制定・公布された新「皇室典範」という法律で規定されている。ここに天皇制の存続する法的根 拠がある。それによれば天皇は戸籍を持たない。従って苗字もない。勤労の義務もなく勿論納税の義務もない。選挙権も なく、被選挙権もない。選挙権については、正しくは「無い」のではなく「停止」という扱いになるらしい。これは戸籍 法による。「戸籍法の適用を受けない者の選挙権・被選挙権は当分の間停止する」と公職選挙法の附則にあり、これが天 皇にも該当するという事らしい。つまり今天皇は選挙権を停止されているのである。又、犯罪を犯しても法的に罪に問わ れる事は決してない。 「皇室典範」にはその他「皇位継承」とか「皇族」「摂政」「敬称」「即位の礼・大喪の礼」など多くの規定が定められ ている。明治22年制定された旧「皇室典範」と比べるとずいぶん簡素化された法律らしいが、ここに、皇位継承は「天皇 の血統に属する男系の男子が継承する」とある。つまり現在日本では Queen は出現しないのだ。 考えてみれば「天皇」というのは実に不思議な存在である。1500年にわたり、君主としてか否かは別にして常にこの 国の盟主として存在し続けてきた。しかもその殆どの期間国の統治権は武士達の手にあったにもかかわらず、二三の特異 な例を除いてその地位が廃絶の憂き目にあう事もなかった。こんな国は他に無い。 さて、天皇談義はその位にして(天皇制について議論し出すとどうしても政治的立場というものに言及せざるを得ず、学問とはかけ離 れた世界へ飛び込んでしまう。)、その天皇家に代々伝わる「三種の神器」の本題に入ろう。 「三種の神器」とは「鏡」「玉」「剣」の三種を言い、皇位を保証する宝物として代々の天皇が継承してきた。一般には、 「八咫鏡」(やたのかがみ)「草薙の剣」(くさなぎのつるぎ)までは良く知られている。玉は「八坂瓊曲玉」(やさか にのまがたま)という。鏡と玉は天照大神の岩戸籠もりの時に造られ、剣は素戔嗚尊が山岐大蛇(やまたのおろち)を退 治したときその尾の中から出現し、霊剣故に素戔嗚が天照大神に献上したとされている。 いずれも日本神話の高天原世界の話であり、現世とは異なるいわば「超空間」での事象だけに、三種の神器と天皇家の結 びつきを強く否定する意見も学会には存在する。 即ち、前期古墳に顕著な鏡・玉・剣を、天皇家の「三種の神器」と結びつけたり、古代豪族の系統に天皇家の祖系をたど ったり、その源流を弥生時代北九州の墳墓に求めようと言う動きなどは、意味がないというわけである。 鏡・玉・剣のセットは、本来民俗祭祀に依代(よりしろ)として用いられてきたものであって、天皇家の神璽とは関わり がないし、前期古墳の鏡・玉・剣セットとも何ら関係なしという。むしろこの民俗祭祀が、「記紀」編纂にあたって神話 の中に取り入れられたのだというのである。これは一つの見方であるが、同じような見解は津田学派と呼ばれる学者達の 中に見受けられる。本来は「人民の宝物」であったと主張したい気持ちも分からなくもないが、これこそなんだか政治的 な臭いがしてしょうがない。 学問的に見て、鏡・玉・剣のセットが民俗祭祀に用いられたという証拠などはどこにもない。むしろ、鄭重に埋葬された 「権力者」や「豪族」と思われる弥生墳墓や古墳からこれらは出土するのである。民俗祭祀の依代よりも、「権力」や 「財力」の象徴として使用された事は明らかである。それ故に、「大和朝廷」を確立し体制・基盤を確固たるものにした 初期天皇家にとってもこれらは宝物だったのである。「三種の神器」をトレースする事の意味は、ただ単にそれらがどん な形状でどんな大きさ重さをもっているかといった興味などではない。「三種の神器」がいかにして「三種の神器」とな っていったか、天皇家はいかにしてこれを皇位継承のシンボルとしたか等々を探る事により、「大和朝廷」成立前後の我 が国の古代にスポットを当てようというものである。好む好まないにかかわらず、「天皇家」と「三種の神器」は強く結 びついている事を認めなければ、古代史研究には踏みこめないと思う。 文献に現れる「三種の神器」を見てみよう。
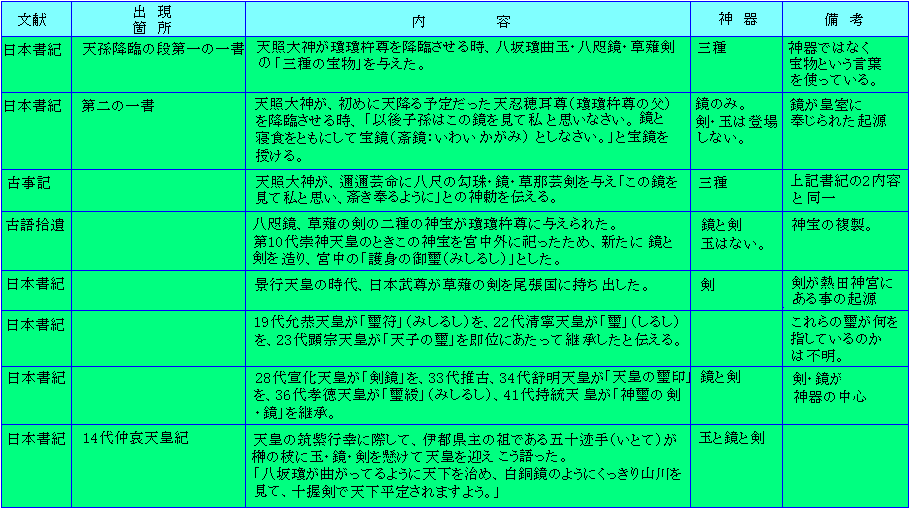
上記の表でご覧いただいたように、ニニギの尊の地上降臨に際して天照大神から授けられた神宝には差違が見受けられる。 表に見られるように「記紀」の時代においては宝物という意味では剣と鏡が中心であったようである。「神器」と言う言 葉が広く定着するのは「南北朝」の頃だとも言われている。 しかし表の最下段に見られるように「鏡・剣・玉」のセットもまた、王権のシンボルとして認識されてはいたのである。 八咫の鏡にいう「八咫」とは一体何だろうか。これは長さの寸法であるとの考えがほぼ定説となっている。手のひらを大 きく広げて親指の先から中指の先(通常の人はこの指が一番長い)までを一咫として、これを八個分つなげた長さの円周 を持つ鏡という説と、1咫は8寸という中国古来の寸法で8咫分(約180cm)という円周を持つ鏡という説とがある。 後者の説がほぼ定説であるが、相当大きい直径を持つ鏡だという事は推測できる。少なくとも手のひらに乗るような大き さではない。この事から、糸島の平原遺跡で発見された鏡、あるいはこれと同等の大きさのものをあてる考えもある。
 上記の伝承からもわかるように、天照大神が授けた神宝には異同があることが見て取れる。しかしいずれの伝承においても、鏡だけは欠くことが出来ないことから、鏡が三種の神器のなかで最も重要なものである事はまちがいないものと思われる。それは、天照大神自らが、これを自分の分身として即ち霊代として崇めるように宣言しているからである。そもそもは天照大神を岩戸の中からおびき出すために鋳造されたものであるが、その光を放つ現象、姿を映すことで神の魂が宿ると考えられていったり、太陽神の崇拝対象としての宝になっていった
ものと思われる。
上記の伝承からもわかるように、天照大神が授けた神宝には異同があることが見て取れる。しかしいずれの伝承においても、鏡だけは欠くことが出来ないことから、鏡が三種の神器のなかで最も重要なものである事はまちがいないものと思われる。それは、天照大神自らが、これを自分の分身として即ち霊代として崇めるように宣言しているからである。そもそもは天照大神を岩戸の中からおびき出すために鋳造されたものであるが、その光を放つ現象、姿を映すことで神の魂が宿ると考えられていったり、太陽神の崇拝対象としての宝になっていった
ものと思われる。天孫降臨とともに地上にもたらされた鏡は、その後の伝承によれば、第10代崇神天皇の時代までは天照大神として宮中に祀られていた。しかし神の勢いが強く、これを恐れた天皇は代替品を造ってこれを宮中に残し、現物は豊鍬入姫命(とよすきいりひめのみこと)に託して宮中外へ運び出させやがて伊勢の地に落ち着いた。これが伊勢神宮(内宮)の起こりであり、八咫の鏡が御神体となった。(古語拾遺)
これを信用すれば現在皇居にある鏡はレプリカという事になる。しかし、「小右記」「御堂関白記」という書物には次のような記事がある。平安時代天徳4年(960年)、内裏に発生した火災のとき、剣と曲玉は持ち出せたが鏡の置いてあった温明殿(賢所、または内侍所とも呼ばれる)は全焼してしまった。しかし、焼け跡から無傷の鏡が3面出てきたというのだ。つまり宝鏡は3体あったことになる。その後も何度かの火災により鏡は焼け出され新たに鋳造したとかいう記事や、破片を拾い集めてそれを御神体としたという記事などが見える。決定的なのは文治元年(1185)、壇ノ浦で平家が滅亡した際、8才の安徳天皇とともに3種の神器は海の底に沈んでいるのである。(もっとも、後に海から拾い上げられたと言う話も残っている。)
現在の皇居には、皇霊殿、賢所、神殿が宮中三殿として並んで建っている。中央の一段と高くなった賢所は天照大神を祀り、ここに鏡が安置されていると言われているが、現在では、天皇自身もこの3種の神器を見ることは許されていない。従って、絹房の中の鏡がどんなものなのかは誰にもわからないのである。これは本家本元の伊勢神宮に置いても同じである。天皇といえどもこの鏡を実見することは出来ないのだ。但し鏡が納められている桐箱の寸法は分かっており、それによれば、直径が49cm以下の鏡だと言うことである。
 「草薙の剣」は有名である。日本武尊(やまとたけるのみこと)が駿河で狩りをしている時に、土地の豪族に野に火を放たれた。この時腰に差していた「天の群雲の剣」がひとりでに抜けて傍らの草むらをなぎ倒した。故に「草薙の剣」と言う。(日本書紀)
「草薙の剣」は有名である。日本武尊(やまとたけるのみこと)が駿河で狩りをしている時に、土地の豪族に野に火を放たれた。この時腰に差していた「天の群雲の剣」がひとりでに抜けて傍らの草むらをなぎ倒した。故に「草薙の剣」と言う。(日本書紀)熱田神宮の御神体であるこの剣は、そもそもの出現はこうである。出雲へ使わされた素戔嗚尊は、櫛稲田姫(くしなだひめ)を助けるために八岐大蛇(やまたのおろち)と戦った。十握剣(とつかのつるぎ)で大蛇の尾を切ったとき、刀の刃が欠けたので見るとなかに剣があり、これは不思議な剣だとして素戔嗚尊は天照大神に献上した。「古事記」にはこの剣は「都牟刈(つむがり)の太刀」と言う名で現れる。本居宣長は「都牟刈」を、「物を鋭く切る」という意味だろうとしているが、こんな表現は他のどんな伝承記事にもなく、本居宣長も自分の想像で言っているだけのようである。「都牟刈」を「丸くなっている」意味だとして、「草薙の剣」を環頭太刀にあてる意見もある。
鏡と同様、ニニギの尊の降臨に伴って「草薙の剣」も再び地上にもたらされる。それ以後の「草薙の剣」の足取りは不明である。第12代景行天皇の時、東国征伐に出かける日本武尊(景行天皇の次男)が、叔母の倭姫命(やまとひめのみこと)から伊勢神宮にあった「草薙の剣」をさずかるのである。どうして剣も伊勢神宮にあるのかについては何も伝承がない。日本武尊は尾張の国で宮簀姫(みやすひめ)と夫婦になるが、伊吹山に荒ぶる神々がいると聞いて、「草薙の剣」を熱田に置いたまま伊吹山へ向かい神々と戦って命を落とす。残された宮簀姫は「草薙の剣」を祀って社を建てる。これが今日の「熱田神宮」だという事になっている。(日本書紀・尾張国風土記・熱田大神宮縁起)
この剣が熱田神宮から宮中へどのように移動したのか、あるいは鏡と同じように複製を宮中へ納めたのかについても何一つ伝承はない。しかし熱田神宮と宮中の二カ所に現在も宝剣は存在している(と思われる)。鏡の項で記したように、宝剣も安徳天皇の入水とともに海底に沈む。後に引き上げられたという話の中でも、この剣は見つからなかったとされており、第84代順徳天皇即位の時(1210)、伊勢神宮の倉から1本の剣が選ばれて三種の神器の一つに加えられた。(その後、壇ノ浦から剣がひとりでに浮かび上がり、その剣をある法師が発見したとかいう話なども現れている。)
熱田神宮には、奉納以来綿々と「草薙の剣」は存在しているという事になっているが、天智天皇の頃一度盗まれた話もある。剣はまた熱田神宮へ戻っている。江戸時代に、熱田神宮の大宮司が神官達4,5人で密かにこの御神体の宝剣を盗み見たという記録があるが、見た者は次々に死んでいき、一人生き残った者がその記録を書いたと言うエジプトの墓荒らしのような話もある。これは記事を書いた書き物が残っているそうなので、ほんとに見た記録なのかもしれない。その記事から想像できる「宝剣」は弥生・古墳時代にかけての遺跡から出土する「有柄細型銅剣」(福岡県三雲遺跡出土。吉野ヶ里からも出土。)に似ていると言う。
勿論、現在宮中にある「宝剣」がどんなものか知る人はいない。

考古学的には曲玉の出現は剣や鏡よりも古い。縄文時代からあり、石や土、時代が降るとガラスや青銅でも造られている。 形もさまざまで長円形のもの、胎児のような形をしたもの、なめらかで曲がったもの(上の写真:この形が一番多い。)な どである。出現は古いが、曲玉が3種の神器に加えられたのは剣や鏡よりも後になってからのようである。津田左右吉は、 ずっと後世まで天皇家の宝物は3種ではなく2種であったと言っている。 「八坂瓊曲玉」(古事記には「八尺の勾珠」と表記されている)の八坂というのは、八咫の鏡の八咫と同じく大きいという 事を表す一般名称だろうとされる。古事記が珠という字を使っている事から丸い真珠の事ではないかという意見もある。珠 とはそもそも、海中に産する玉のことを言うからである。 「記紀」伝承には天照大神が勾玉を身につけている事が記されている。伊弉諾尊(いざなぎのみこと)によって高天原を追 放された素戔嗚尊は、姉の天照大神に別れを告げるため高天原を訪れる。弟の姿を見て天照大神はまた狼藉に来たのではな いかと疑い、誓約(うけい)を行う。 その時天照大神の勾玉から男神が生まれる。この伝承に現れる勾玉の正式な名前は「八尺の勾珠の五百津(いおつ)の美須 麻流(みすまる)の珠」という。美須麻流(書紀では御統)とは、曲玉や菅玉を一本の紐で繋ぎ、腕輪や首に懸けるように したものを言う。つまりペンダントのようなものである。また天照大神の岩屋籠もりの際、真坂木(まさかき:榊)に「八 坂瓊曲玉」が懸けられている。これらの伝承を見ても、玉が相当昔から神々たちにも用いられていたことがわかる。 しかしながら、曲玉と三種の神器との関係は不明である。どうやって三種の神器になったのかの伝承は一切ない。だが現に 今も宮中に「玉」は存在しているし、平安時代には既に「玉」を納めた「璽箱」(しるしのはこ)が、天皇の側にある。記 録によれば、第95代花園天皇(1308年即位)の日記に、箱には鍵がつけられ、青い絹で包まれており、四方から紫の紐で 結ばれているとある。また、この時代既に、「開けてはならない」とされている。歴代の天皇の何人かは開けてみようとし たり(第63代冷泉天皇は紐をほどいたら白い煙が出てとりやめたという。)、 揺すってみたり(第84代順徳天皇)したようである。現在「八坂瓊曲玉」は、御所の「剣璽の間」に草薙の剣とともに安置 されている。運んだ事のある侍従の話では、何か拳(こぶし)大のものが入っているように感じたとの事である。 見てきたように、「三種の神器」の実体は現在確かめるすべもない。天皇家当主である天皇自身も実見を許されていないの であれば、誰にも実物を見るチャンスはない。即位の礼では中身は確かめず、儀礼的に箱のままあるいは袋のまま継承式を 行っているのである。しかし、「剣」と「鏡」と「玉」が天皇家の「三種の神器」であることは疑いない。天皇家が一体い つ頃日本の盟主となったかについては不明であるが、少なくともこれらが「宝物」であった時代であるのも間違いないだろ う。そして多くの古墳から出土する遺物を見ても、これらが、その古墳の主が死後の世界まで持っていきたがる程の「宝物」 であった事も我々は知っている。また古墳の主の大半は、騎馬民族も含めたはるか大陸・朝鮮半島からの「渡来人」であっ た事も今日ほぼ確定的である。


天皇家がいつ頃天皇家として確立したか、ここまでの考察でほぼ解明されたのではないだろうか。古墳時代である。その萌 芽は弥生時代にある。一部の人々を除き、今日我々は「天皇家」を容認している。「可哀想だから平民に戻せ!」という声 も聞かないし、崇め奉って「神様だぞ!」という運動もない。あくまでも「象徴」として日本に存続し続ける事を、現代の 我々は選択している。おそらく、天皇自身が言い出さない限りこの状態は続いていくと思われる。そこに、日本人の日本人 たる由縁が隠されているような気がしないでもない。
皇居のご神体、59年ぶり「動座」 建物の耐震診断で 2004.6.18 Asahi.com ------------------------------------------------------------------------------------------ 宮内庁が、皇居内の宮中三殿の耐震性や劣化状況を調べることになり、いわゆる「三種の神器」の一つで伊勢神宮にまつら れている鏡のレプリカとされる神体などを一時、隣接の仮殿(かりでん)に移す「動座」の儀式が18日、あった。神体な どは調査終了後の来月27日まで「一時避難」する。「動座」は、戦時中に空襲を避けて一時、地下庫に移されて以来59 年ぶり。宮中三殿は、天皇の祖先神をまつる賢所(かしこどころ)、歴代天皇、皇族の霊をまつる皇霊殿(こうれいでん)、 八百万(やおよろず)の神々をまつる神殿が並ぶ。いずれも小ぶりな銅瓦ぶきの入り母屋造り。建物が築後約115年たつ ため、木材の強度などを調べることになった。計約5600万円を公費である宮廷費から支出するという。皇室の宗教施設 への公費支出となるが、同庁は「三殿は『皇位とともに伝わるべき由緒ある物』で公的色彩を持つため、国費を支出できる」 としている。 (06/18 10:30)皇居・宮中三殿を出て仮殿に向かうご神体を乗せた「御羽車」=18日午前9時32分、代表撮影

邪馬台国大研究・ホームページ
 日本古代史の謎/ 三種の神器
日本古代史の謎/ 三種の神器