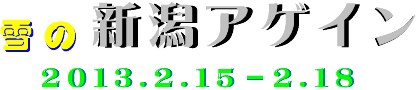
2013.2.16(土曜日)


 Music: 星に祈りを
Music: 星に祈りを
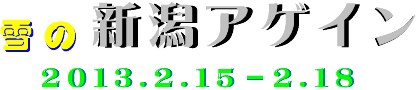


阿賀野市 阿賀野市(あがのし)は、新潟県北東部に位置する市である。2004年4月1日に新潟県北蒲原郡安田町、水原町、京ヶ瀬村、笹神村の 4町村が合併して市制施行された市で、阿賀野川流域にあることからこの名前となった。市役所は旧水原町にある。旧水原町内の瓢 湖(「白鳥の湖」で知られる。)や、旧笹神村内の五頭山、五頭温泉郷などがある。 新潟市のベッドタウンの側面も持つ。 阿賀野市は、新潟平野のほぼ中央に位置し、南側に大河阿賀野川が流れ、東側に標高1000m級の山々が連なる五頭連峰を背にして形 成された扇状地に、6500ha余りの水田が広がる穀倉地帯である。 県都新潟市から南東へ約20km、東は新発田市、阿賀町、西は新潟市、南は五泉市、阿賀町、北は新潟市、新発田市にそれぞれ接して いる。磐越自動車道と国道49号が南北に、国道460号と290号・JR羽越本線が東西に走り、大都市に近い自然環境豊かな地域である。

五頭連峰の麓には「野中遺跡」や「ツベタ遺跡」など、笹神(ささかみ)丘陵やその麓には「上野林遺跡」など石器時代〜縄文時代 や弥生時代およびそれ以降の遺跡が多数発掘されており、2万数千年前から1万3千年前の石器時代の遺跡「上野林遺跡」からは、 氷河時代と推測される新潟県最古の石器が見つかっている。(旧安田町) 縄文時代の「野中遺跡」や「ツベタ遺跡」(旧安田町)からは、ストーンサークル(環状列石)や、大地震による液状化跡や地割れ の跡等も見つかっている。
<再葬墓> 遺体をいったん埋葬して白骨化させたあと、その骨を再び壷形土器などの容器に埋納する葬法である。土器棺を用いた再葬墓は、 縄文時代晩期後半の近畿地方から東海地方、中部地方にも見られるが、弥生時代前期から中期に東海から東北地方南部に分布す る再葬墓は、壷形土器を土器棺とすることに特徴がある。 また、焼人骨葬は縄文時代晩期に中部高地を中心として散見され、弥生時代になると関東から東北地方南部に分布する。抜歯形 式、加工人骨もほぼ同じ範囲にみられる共通した特徴があり、祖先崇拝と関連した埋葬形態であったと考えられる。再葬墓は土 坑の中に壷形土器を一個体から数個体納めることを常とする。 新潟県内の弥生時代前期、中期の再葬墓としては、村尻遺跡、猫山遺跡、六野瀬遺跡、大曲遺跡、三ノ輪遺跡などがある。保明 浦遺跡では地点を異にして、深鉢やカメ形土器が納められた縄文時代晩期終末の土坑、壷形土器が主として納められた弥生時代 前期、中期土坑がみられた。
上の写真、上から二段目左端の石器は、独鈷(どっこ)石と呼ばれるもので、縄文時代晩期の「横峯A遺跡」から出土。長さ20cm位。 密教仏具の独鈷に似ていることから独鈷石と呼ばれる。独鈷石は祭器の一種と言われ、北海道から九州まで全国各地で出土している。 阿賀野市では、旧安田町の「藤堂遺跡」からも出土しているそうだが、用途は不明である。その上の石器も独鈷石に近い。
弥生時代前期から中期にかけての「猫山遺跡」(阿賀野市旧京ヶ瀬村)から出土した深鉢。 この遺跡からは、翡翠の勾玉、石鏃等も出土しているが、稲作の痕跡は無く、縄文時代の 色合いを濃く残している。(新潟県埋蔵文化財センター)
奈良時代から平安時代の旧笹神村の官衙(かんが=官庁)遺跡と推定される発久(ほっきゅう)遺跡からは、延暦14年(795)の ものと推測される月朔干支(げっさくかんし)を書き連ねた簡便な暦の木簡(もっかん)が発掘されている。 平安時代末期の長承(ちょうじょう)三年(1134:崇徳天皇)に、現在の阿賀野市のほぼ全域と新潟市の一部が皇嘉門院(こうか もんいん=藤原聖子(崇徳天皇の皇后、藤原忠通の娘))の荘園(白河荘)にされた。その後、越後の白河荘は、治承(じしょう) 四年(1180:高倉天皇)に源頼朝より伊豆の大見氏(大見郷(現.伊豆市)に土着した桓武平氏の後裔)が地頭に補任した。
南北朝時代の貞和年間(1350年頃)、南朝に仕えた篠岡中将資尚により笹岡城が築城される。戦国時代にはいるとこの笹岡城は、 上杉景勝・直江兼続の新発田攻めの前線基地となった。

 邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部Annex/ 新潟アゲイン
邪馬台国大研究/ 歴史倶楽部Annex/ 新潟アゲイン