2007.5.23 with 添田さん

東本願寺 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 所在地 京都府京都市下京区烏丸通七条上ル二丁目常葉町754番地 宗派 大谷派本山 本尊 阿弥陀如来 創建年 慶長7年(1602年) 開基 教如 別称 東本願寺、お東さん 文化財 教行信証(国宝)絹本著色親鸞聖人像他(重要文化財) 京都タワーからの東本願寺東本願寺(ひがしほんがんじ Higashi Hongan-ji)は、京都府京都市下京区にある浄土真宗の仏教寺院。 真宗教団連合(真宗十派)の一つ真宗大谷派の本山で、西本願寺(浄土真宗本願寺派の本山〈正式名称・本願寺〉)と並ぶ浄土真 宗の本山である。正式の寺号は1987年までは「本願寺」、同年以降は「真宗本廟」(しんしゅうほんびょう)。同じ下京区にある 西本願寺と区別するため、「お東さん」と呼ばれることが多い。 <概要> 本願寺の第12代教如(光寿)が、徳川家康によって本願寺の東に寺領を与えられ、1602年に本願寺が二つに分かれたとき、教如が 開いた。現在の京都市下京区烏丸七条に位置し、堀川七条に位置する本願寺の東にあるため、東本願寺と称されるようになった。 1987年には、大谷派と包括・被包括の関係にあった宗教法人としての本願寺が法的に解散され、宗派と一体のものとされた。以後、 東本願寺の正式名称は「真宗本廟」(「本廟」とは、同信同行の門信徒が宗祖親鸞の教えを聞信する根本道場・帰依処としての、 親鸞の「はかどころ」の意)となる。分派した浄土真宗東本願寺派と区別を付け、正当性を主張する意味もある。⇒お東騒動 江戸時代に4度の火災に遭っており、その火災の多さから「火出し本願寺」とのあだ名もあるほどで、現存建造物の多くは明治期 の再建だが、建築・障壁画等は当時の技術の粋を集める。親鸞聖人像を安置する御影堂は世界最大級の木造建築物である(現在保 護屋根に覆われ大修復工事中)。また、御影堂門は京都三大門の一つである。親鸞自筆の教行信証(国宝)を所蔵。近接する飛地 境内地の渉成園は国の名勝。現門首は大谷暢顕(浄如)。 <文化財> 国宝 教行信証 親鸞筆(坂東本)6冊 重要文化財 絹本著色親鸞聖人像(安城御影) 紙本著色本願寺聖人親鸞伝絵(弘願本) 4巻 紙本著色本願寺聖人伝 絵康楽寺円寂、宗舜筆 4巻 一念多念文意 親鸞筆 <アクセス> 地下鉄烏丸線五条駅下車

「お東さんのローソク」と呼ばれる京都タワーがよく見える。

御影堂門。知恩院三門、南禅寺三門とともに京都三門のひとつ。

御影堂(修復中)。親鸞聖人像を安置する御影堂は畳927枚もある広さ。ちなみに御影堂はこちらでは「ごえいどう」と呼ばれている。 真宗大谷派の本山である東本願寺は正式には真宗本廟(しんしゅうほんびょう)という。親鸞聖人によって本願寺が開かれ、慶長7年 (1602)に徳川家康より寄進を受けた教如上人が、東本願寺として分立したのが始まりとされる。東本願寺に対し、それまでの本願寺 は西本願寺と呼ばれるようになった。その後4度の火災に遭うが、その度に建て直され、現在の建物は明治28年(1895)に再建され たもの。 東西200m、南北400mの広大な敷地には巨大な伽藍が立ち並んでおり、中でも親鸞聖人の像を安置してある御影堂は、幅76m、 奥行58m、高さ38mの大きさを誇る世界最大級の木造建築。その御影堂と本堂の阿弥陀堂への渡り廊下には、再建の際に、巨材を 引くために全国の女性門徒が寄進した毛髪でよりあげた「毛綱」が展示されている。ここより東へ徒歩7分のところに、東本願寺の別邸 である渉成園(しょうせいえん)がある。


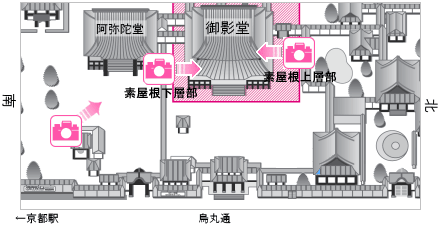

御影堂門 京都三大門の一つで、楼上の正面には浄土真宗の聞法の根本道場であることをあらわす「真宗本廟」の額が掲げられている。楼上の堂 内には、中央に釈迦如来、左に阿難尊者、右に弥勒菩薩の三尊像が安置されている。これは、釈尊(釈迦)が阿難尊者、弥勒菩薩に、 真宗の根本経典である『仏説無量寿経』(大無量寿経)を説いたことあらわしている。この門から教えに入り、また、その門を出るこ とは、新たな人生の出発が始めることを意味している。


阿弥陀堂 本尊・阿弥陀如来を中心に、その左右には親鸞聖人が「和国(日本の国)の教主」として仰がれた聖徳太子をはじめ、今を生きる日本 人に阿弥陀如来の願いを「南無阿弥陀仏」という真実の言葉によってあきらかにし、親鸞聖人に本願の教えを伝えた、七高僧といわれ る龍樹・天親(インド)、・曇鸞・道綽・善導(中国)、源信(日本)、そして法然上人の7人の御影が掛かっている。

私の「邪馬台国大研究」HPをよくご覧いただいていて、特に遺跡めぐり、博物館めぐりの、歴史倶楽部例会の軌跡をたどってお られる北九州市の添田さんが、京都へ来られるというのでさっそくお会いした。添田さんは、我々が泊まった民宿にもそのまま泊 まり、おかみさんと我々の話をしてくるという徹底振りで、ありがたいやら恥ずかしいやらと言った処だが、このHPも少しは歴 史ファンのお役に立っているようである。お開きしたばかりの鴨川の河床で、歴史談義に花を咲かせた。

邪馬台国大研究 / 歴史倶楽部ANNEX / 東本願寺
 SOUND:Penny Lane
SOUND:Penny Lane