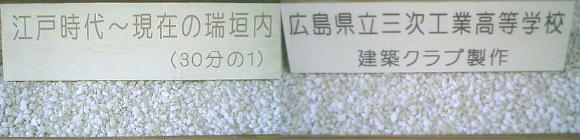みなさんが立っている足元が、宇豆柱の跡である。原寸大で位置表示が復元してある。

何度見ても恐るべき太さだ。これがそびえていた古代の出雲大社を是非見てみたいものだ。
雲太(うんた):古代出雲大社復元展示館
と思ったら、出雲大社のすぐ前に「雲太(うんた)」と名づけられた古代出雲大社の復元模型を展示している 資料館ができていた。これはいい。これを見れば古代のイメージが沸いてくる。
これだけのものが作れる権力は並のものではない。やはり、大和とも北九州とも違う勢力の存在を考えたほうが 自然だろう。

稲佐の浜は出雲大社の西側にある。高天原と出雲の、国譲り交渉の場である。3度目の高天原の使者天鳥船神と 建御雷神は、この浜の波間に剣を逆さに突き立て、その上にあぐらをかいて談判を開始する。大国主命の子建御 名方神は承知せず、力比べをする。そして建御名方神は敗れ、建御雷神に追われて信濃の諏訪まで逃げていく。 かくて国譲り交渉は妥結、調印となる。 また、11月の神無月(かんなづき)は、出雲では神有月(かみありづき)と呼ばれる。全国の神々が出雲に集 結し、この稲佐の浜から上陸する。そして神々の先導役、大国主の使者として、竜蛇さま(海蛇)がこの時期に浜 にやってくる。 <神迎祭> 出雲大社HPより 11月24日午後7時 稲佐浜−神楽殿−東西十九社 神在祭に先立つ旧暦10月10日の夜7時、国譲りの聖地稲佐浜において行われる、 全国各地より参集される神々をお迎えする神事です。これは竜神の先導にて、神々が海原遥か出雲にご参集にな るという古き伝えのままに行われるものです。稲佐浜から大社までのご神幸では、曲げ物に鎮座された竜蛇さま を先頭に、真白い絹垣の内に坐す神々が大国主大神の待たれる大社へと向かわれます。 大社に着かれると、神楽殿において国造(こくそう)以下全祀職の奉仕により、ここでも神迎祭が執り行われ、 これが終わるとようやく神々は旅(宿)社である東西の十九社に鎮まられます。神々ご案内の竜蛇さまは、豊作 や豊漁・家門繁などの篤い信仰があります。神迎祭終了後には特別拝礼、さらに神在祭期間中にも八足門内廻廊 に竜蛇さまを奉祭し、一般の自由参拝ができます。 伊耶佐の小浜(稲佐浜)「古事記」 -------------------------------------------------------------------------------- ここに、天照大御神詔(の)らししく、「また、いづれの神を遣はさば吉(え)けむ」 しかして、思金(おもひかね)の神またもろもろの神の白(まを)ししく、「天の安の河の河上の天(あめ)の石屋 (いはや)に坐(いま)す、名は伊都之尾羽張(いつのをははり)の神、これ遣はすべし。もしまた、この神にあら ずは、その神の子、建御雷之男(たけみかづちのを)の神、これ遣はすべし。また、その天(あめ)の尾羽張(おは はり)の神は、逆(さかさま)に天の安の河の水を塞(せ)き上げて、道を塞き居るゆゑ、他神(あたしかみ)は得行 かじ。かれ、別(こと)に天(あめ)の迦久(かく)の神を遣はして問ふべし」 かれしかして、天の迦久の神を遣はして、天の尾羽張の神に問ひたまひし時に、答へ白(まを)ししく、「恐(か しこ)し。仕へ奉らむ。然れども、この道には、僕(あ)が子建御雷(たけみかづち)の神を遣はすべし」とまをし て、すなはち貢進(たてまつ)りき。しかして、天(あめ)の鳥船(とりふね)の神を建御雷の神に副(そ)へて遣は したまひき。 ここをもちて、この二はしらの神、出雲国の伊耶佐(いざさ)の小浜(をばま)に降(くだ)り到りまして、十掬釼 (とつかつるぎ)を抜き、逆(さかさま)に浪の穂に刺し立て、その釼(つるぎ)の前(さき)に跌坐(あぐみゐ)て、 その大国主の神に問ひて言(の)らしくく、「天照大御神・高木(たかぎ)の神の命以ちて、問ひに使はせり。汝 (な)がうしはける葦原(あしはら)の中(なか)つ国は、我(あ)が御子の知らす国と言(こと)依(よ)さしたまひき。 かれ、汝(な)の心いかに しかして、答へ白(まを)ししく、「僕(あ)は得(え)白さじ。我(あ)が子八重事代主(やへことしろぬし)の神、 これ白すべし。然るに、鳥の遊び・取魚(すなそり)して、御(み)大(ほ)の前(さき)に往(ゆ)きて、未だ還り来 ず」 かれしかして、天の鳥船の神を遣はし、八重事代主の神を徴来(め)して問ひたまひし時に、その父の大神に語 りて言ひしく、「恐(かしこ)し。この国は天つ神の御子に立て奉らむ」 といひて、すなはちその船を蹈(ふ)み傾(かたぶ)けて、天(あめ)の逆手(さかて)を青柴垣(あをふしがき)に打 ち成して隠(かく)りましき。 -------------------------------------------------------------------------------- 上は古事記の「国譲り」の場面だが、「日本書紀」では内容が少し異なる。高皇霊産神が経津主神と武甕槌神を 遣わし、大国主神は大己貴神と名を変え、天降った場所は、五十田狭の小汀とある。

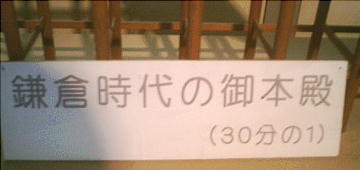
稲佐の浜
この後「和鋼博物館」を経て大阪へ帰宅。



邪馬台国大研究 /歴史倶楽部/ 再び山陰へ