 Music: Carpenters
Music: Carpenters
戝榓孲嶳
2004.9.25乮搚乯
楌巎嬩妝晹戞88夞椺夛
廐嬻偺壓傪丄摏堜弴宑丒朙恇廏挿偺忛壓挰偐傜朄棽帥傊
戞俉俉夞椺夛埬撪
応強丂丂丂丗撧椙導戝榓孲嶳巗乮弌敪亖嬤揝戝榓孲嶳墂丂摓拝亖朄棽帥乯
擔帪丂丂丂丗俋寧俀俆擔乮搚乯
廤崌応強丂丗俙俵俉丗係侽嬤揝揹幵側傫偽墂乮戝嶃慻乯
丂丂 丂丂撧椙偺恖偼俋丗俁侽傑偱偵乽戝榓孲嶳墂乿傊廤崌偟偰壓偝偄丅
旓梡丂丂丂丗岎捠旓乮戝嶃慻540墌亄620墌乯丄亄丂斀徣夛旓梡
帩嶲偡傞暔丗曎摉丅塉嬶丄懼偊忋壓拝摍乆乮塉嬶偼偍朰傟柍偔丅乯
峴掱丗丂 丂丂側傫偽墂(8:53乯亅撧椙慄夣懍媫峴亅惣戝帥拝乮9:22乯9:24敪 亅乮妧尨慄媫峴乯亅戝榓孲嶳墂乮9丗29拝乯
嬤揝戝榓孲嶳墂 伀丂娵嶳屆暛 伀丂戝擺尵捤丂伀丂峳栘枖塃塹栧摴応愓丂伀丂僉儕僔僞儞弣嫵旇丂伀丂塱宑帥丂伀丂孲嶳忛毈丂伀丂
弔妜堾丂伀丂梾忛栧愓丂伀 攧懢恄幮 伀丂旴揷娐崐廤棊 伀丂帨岝堾丒榋摴嶳屆暛 伀丂彫愹忛愓丒彫愹恄幮丂伀丂拞媨帥愓丂伀丂
朄棽帥嫬撪 丂伀丂摗僲栘屆暛丂伀丂俰俼朄棽帥墂
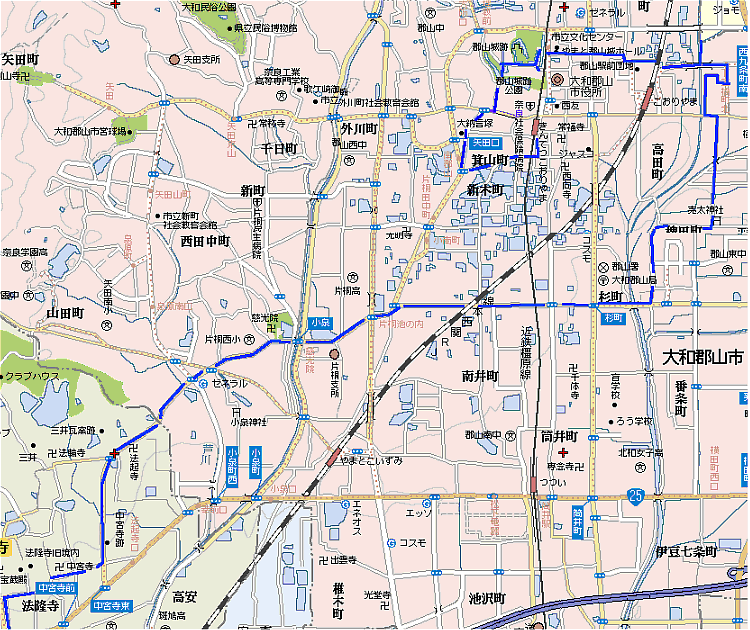
亙戝榓孲嶳巗偺増妚亜丂乮戝榓孲嶳巗俫俹懠傛傝乯
撽暥帪戙乮斢婜乯偺乽壓抮堚愓乿
墶揷挰廤棊偺杒曽偵偁傞壓抮偱丄搚嵒嵦庢拞偵栱惗幃搚婍傗愇曪挌丄搚巘婍偑傒偮偐傝丄抮偺拞墰晹偐傜偼丄
堜屗傗撽暥幃搚婍傕悢揰敪尒偝傟偰偄傞丅
栱惗帪戙偺乽屆壆晘堚愓乿
枮婅帥挰屆壆晘偺搶杒抧懷偱丄栱惗幃搚婍偲愇孄偵崿偠偭偰愇鑆乮偣偒偧偔丒愇偺傗偠傝乯偑尒偮偐偭偰偄
傞丅愇孄偵偼斾妑揑戝偒側傕偺偑偁傝丄憡摉側婯柾偺廧嫃愓偲峫偊傜傟偰偄傞丅
乽惣揷拞堚愓乿
惣揷拞挰偺搶撿偱丄栱惗幃搚婍曅傗愇婍偑敪尒偝傟偨丅徍榓58擭偺敪孈挷嵏偱偼扜寠幃廧嫃丒搚氎乮偳偙偆丒
搚偺偁側乯丒僺僢僩丒峚側偳偄偢傟傕栺2000擭慜偺栱惗帪戙拞婜偺堚峔偑敪尒偝傟丄悢懡偔偺搚婍傗愇婍傕弌
搚偟偰偄傞丅扜寠幃廧嫃愓偼丄捈宎栺俉嘼偺墌宍偺暯柺宍傪傕偮戝偒偝偱丄拞墰偵楩愓偑偁傝丄奃偑岤偔懲愊
偟偰偄偨丅攔悈峚偑奜偵岦偐偭偰偺傃丄楩偺傑傢傝偵偼拰寠偑偁偭偰廧嫃偺壆崻傪巟偊偨庡拰偲悇掕偝傟傞丅
屆暛帪戙
丒乽彫愹戝捤屆暛乿
彫愹挰戝捤偵偁傞丅栴揷媢椝偺搶撿抂偵偁傞係悽婭崰偺屆暛偱丄巗撪偱偼嵟傕屆偄丅慡挿栺80m丄慜曽晹偺暆
栺40m丄崅偝栺俀m丄屻墌晹偺宎栺50m丄崅偝栺俈m偺慜曽屻墌暛偱丄戭抧憿惉偺偨傔慜曽晹偲屻墌晹偺廃曈偑嵦
搚偝傟偰丄尰嵼偱偼墌暛偺傛偆側忬懺偵側偭偰偄傞丅挷嵏偺帪偵丄搚巘婍丒嬀俁柺丒寱侾岥丒搧侾岥側偳偑弌
搚偟偰偄傞丅亀戝榓柤強恾夛亁偵乽愒瀺曟彫愹懞偵偁傝丄愒瀺偼暔晹庣壆傪幩偨傝偟恖栫乿偲偁偭偰丄偙偺捤
偑愒瀺乮偄偪傃乯偺曟偲揱偊傜傟偰偒偨丅
丒乽榋摴嶳屆暛乿
彫愹挰榋摴偵偁傞丅慜曽屻墌暛偱丄暛媢偺庡幉慡挿栺100m丄屻墌晹偺宎栺75m丄崅偝栺14m丄慜曽晹偺暆栺50m丄
崅偝栺俇m偺俁抜抸惉偱丄柺愊俇悿俆曕偲婰榐偝傟姱桳抧偱偁傞丅帨岝堾偺撿偵偁偨傞偺偱帨岝堾嶳偲傕屇偽
傟俆悽婭弶摢崰偺屆暛偲峫偊傜傟偰偄傞
丒乽妱捤屆暛乿
徍榓53擭係寧20擔巗巜掕暥壔嵿乮巎愓乯偱愮擔挰偵偁傞丅栴揷媢椝偺堦巟柆偺愭抂偵抸偐傟偨屆暛丅捈宎栺49m丄
崅偝栺4.5m偺墌暛偱丄捀忋偵偼搻孈偝傟偨偲巚傢傟傞戝偒側偔傏傒偑偁傝丄偙偺偨傔偵妱捤乮幵捤乯偺柤偱屇
偽傟偰偒偨丅徍榓43擭敪孈挷嵏偑峴傢傟丄撿偵岦偐偭偰奐岥偡傞墶寠幃愇幒傪庡懱晹偲偡傞屆暛偱偁傞偙偲偑
敾柧偟偨丅尯幒偐傜偼偔傝敳偒幃偺壠宍愇娀偑敪尒偝傟偨丅傑偨丄暃憭昳偲偟偰嬀侾柺丒悅壓幃帹忺俀懳丒悈
徎惢愗巕嬍丒暽嬍乮傊偒偓傚偔乯惢悰嬍側偳偑偁傝丄娀偺廃曈偐傜偼攏嬶丒漦峛丒揝鑆丒恵宐婍側偳偑弌搚偟
偨丅俇悽婭慜敿偺抸憿偲巚傢傟傞丅偦偺屻丄搻孈慜偺尨宆偵栠偝傟丄挰撪偺椢抧岞墍偲偟偰曐懚偝傟偰偄傞丅
丒乽嶚旜屆暛乿
彫愹挰偵偁傞丅徍榓56擭11寧崙棫椕梴強徏廑憫撪偺廻幧偺婎慴岺帠偺嵺丄愇幒偑敪尒偝傟丄梻57擭俀寧曐懚偺
偨傔偺敪孈偑峴傢傟偨丅暛媢偼墌宍丄宎栺27m丄廃埻偵暆栺係m偵傢偨傞廃峚偑嶌傜傟偰偄傞丅撪晹偺愇幒偼椉
懗幃墶寠幃偱丄尯幒偺挿偝偼4.5m丄暆偼杒嬿偱2.17m丄拞墰偱2.63m丄撿嬿偱2.6m丅愇幒撪偵偼壠宍愇娀偺攋曅
偑嶶棎偟偰偄偨丅傑偨丄慉摴乮偣傫偳偆乯偺杒敿晹傪拞怱偵栘娀嵽傗偦偺廃埻偵揃偑偐偨傑偭偰弌搚偟丄戝棟
愇惢偺愇懷乮弰曽乯偑俁屄弌搚偟偰偄傞偺偱屻悽偺捛憭傕峫偊傜傟傞丅屆暛偼俇悽婭偐傜俈悽婭慜敿偺抸憿偲
悇掕偝傟傞丅
榓摵3擭乮710乯搒偑旘捁乮摗尨嫗乯偐傜暯忛乮側傜丄暯忛嫗乯偵堏傝丄搒偺撿嫗廔偵偼梾忛栧偑偁偭偰丄偙偺
搒偺峹奜偵偼戝媨恖偺偨傔偺曐梴強乽栻墍媨乿偑偁傝丄搶戝帥椞惔悷彲偵懏偟帥椞乽孲嶳乿乮墳曐2擭丄1162乯
偲屇偽傟偰偄偨丅
偦偺屻丄拞悽枛婜偺崿棎婜傪宱偰丄怐揷怣挿偲慻傫偩摏堜弴宑乮乽摯働摶傪寛傔崬傫偩乿偲偄偆尵梩偺儖乕僣乯
偑戝榓傪摑堦偟丄揤惓8擭乮1580乯摏堜偐傜孲嶳偵堏傝丄柧抭岝廏偺巜摫偱忛妔偺惍旛偵偐偐偭偨丅偲偙傠偑丄
杮擻帥偺曄偐傜嶳嶈偺崌愴傑偱偺戝憶摦偲側傝丄弴宑偺巰屻傪宲偄偩掕師偑撍慠廏媑偐傜埳夑忋栰傊崙懼傪柦
偠傜傟偨屻丄揤惓13擭乮1585乯朙恇廏媑偺掜丄戝擺尵廏挿偑孲嶳忛偵擖傝丄婭埳丄榓愹丄戝榓嶰働崙偱昐枩愇
傪椞偟丄婭廈崻棃帥偺戝栧傪忛栧偵偟偨傝丄廃曈偺恄幮丄暓妕偐傜暓愇丄曟愇摍丄偁傞偄偼弔擔墱嶳偐傜戝愇
傪愗傝弌偟塣傃丄忛妔偺戝憹抸偲忛壓挰傪寶愝偟偨丅
偦偺屻悈栰丄徏暯丄杮懡摍悢戙偺忛庡偺屻丄嫕曐9擭乮1724乯5戙彨孯摽愳峧媑偺懁梡恖傪偮偲傔偨桍郪媑曐偺
巕丄媑棦偑峛晎傛傝揮偠侾俆枩愇傪埲偭偰擖晹丄2戙栚怣崈埲壓忢偵暥帯偵廏偱偨斔庡偵宐傑傟丄忛壓傪拞怱偲
偟偰丄恄妛丄崙妛丄娍妛丄攐鎫丄拑摴丄壴摴側偳偑塰偊丄峕屗帪戙偵嬥嫑梴怋丄愒晢從偑偝偐傫偲側偭偨丅桍
郪斔偺廳恇偱攷妛懡寍摿偵彂夋傪傛偔偟偨丄桍棦嫳側偳戙昞揑側暥恖傕弌丄惌帯宱嵪偺幚妛偵偡偖傟偨庲妛幰丄
孎戲斪嶳丄寱弍巜撿栶丄峳栘枖塃塹栧側偳傕廧傫偱偄偨丅
傑偭偨偔偗偟偐傜傫帠偵丄戝榓孲嶳偱偼丄偙偙偑幾攏戜崙偩偲徧偟偰丄儈僗斱栱屇僐儞僥僗僩側傫偧傪
傗傜偐偟偰偄傞丅壗偱傕偐傫偱傕丄尵偊偽偄偄偭偪傘偆傕傫偠傖側偄偑丅





 丂
丂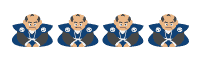
乽戝榓孲嶳丒娵嶳屆暛丒戝擺尵捤乿
乽僉儕僔僞儞弣嫵旇丒塱宑帥乿
乽孲嶳忛毈丒弔妜堾乿
乽梾忛栧愓丒旴揷娐崐廤棊丒攧懢恄幮乿
乽彫愹恄幮丒帨岝堾丒榋摴嶳屆暛乿
偦傟偱偼丄忋傪僋儕僢僋偟偰戝榓孲嶳偺楌巎傪偍妝偟傒壓偝偄丅堦斣忋偐傜弴孞傝偵愭傊恑傓帠傕偱偒傑偡丅
 幾攏戜崙戝尋媶伟淹甙嫁 乛 INOUES.NET 乛丂戝榓孲嶳
幾攏戜崙戝尋媶伟淹甙嫁 乛 INOUES.NET 乛丂戝榓孲嶳
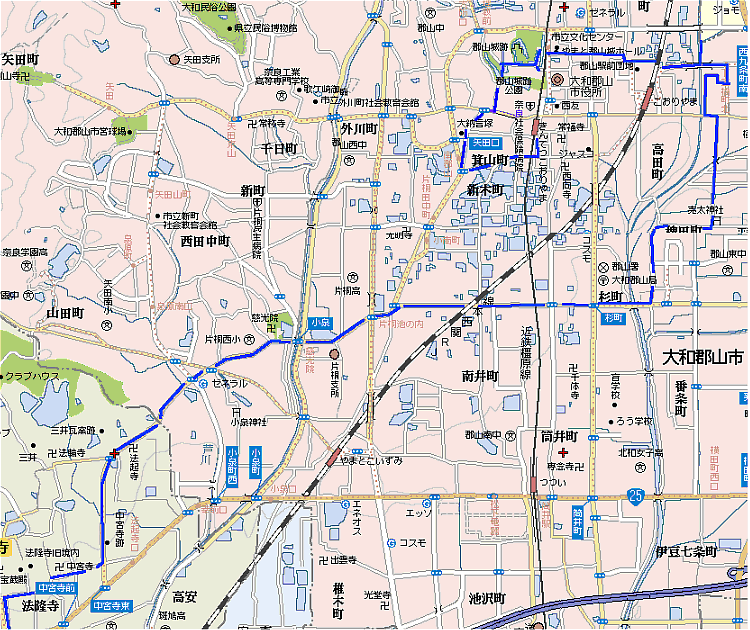
 Music: Carpenters
Music: Carpenters
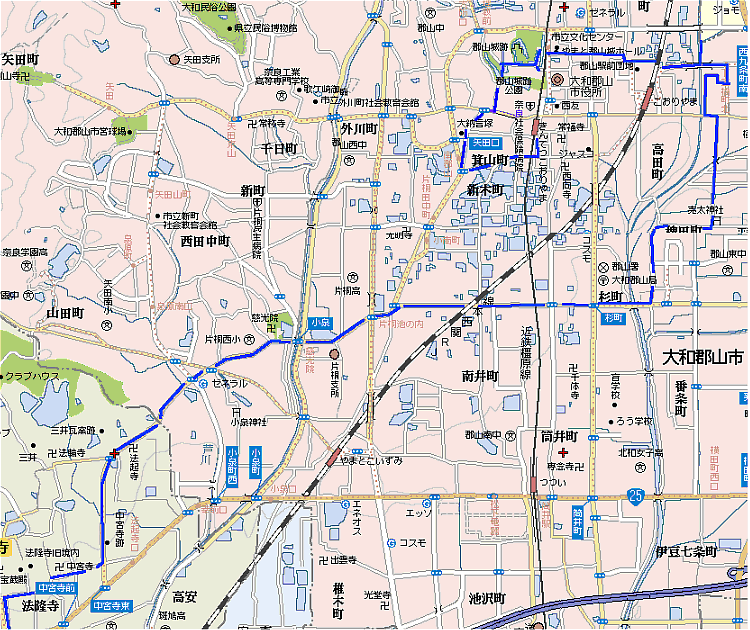





 丂
丂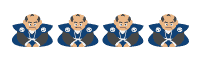
 幾攏戜崙戝尋媶伟淹甙嫁 乛 INOUES.NET 乛丂戝榓孲嶳
幾攏戜崙戝尋媶伟淹甙嫁 乛 INOUES.NET 乛丂戝榓孲嶳